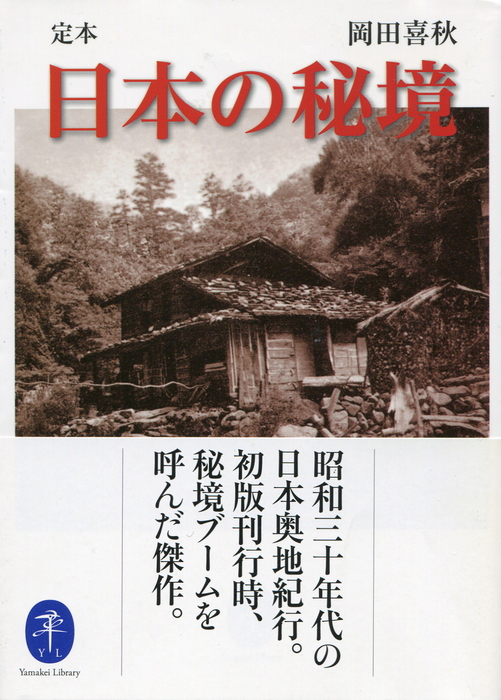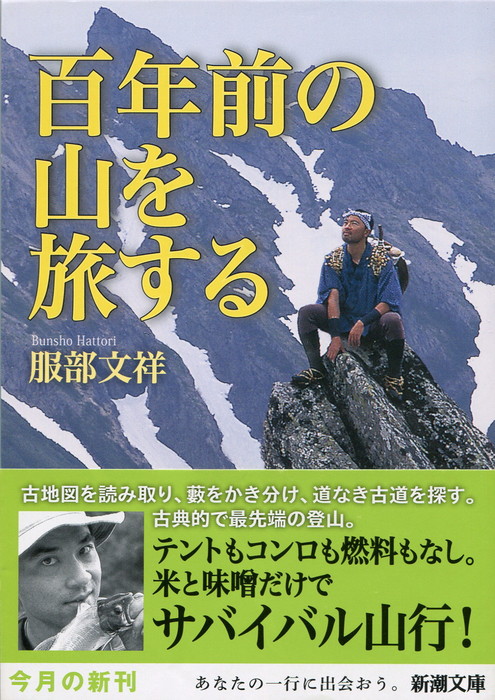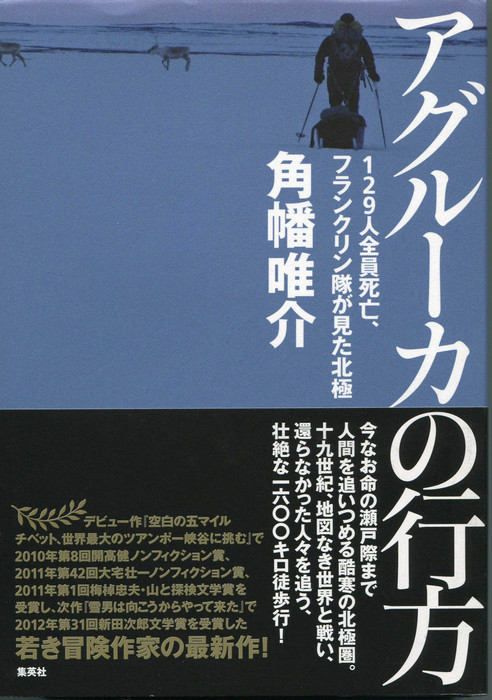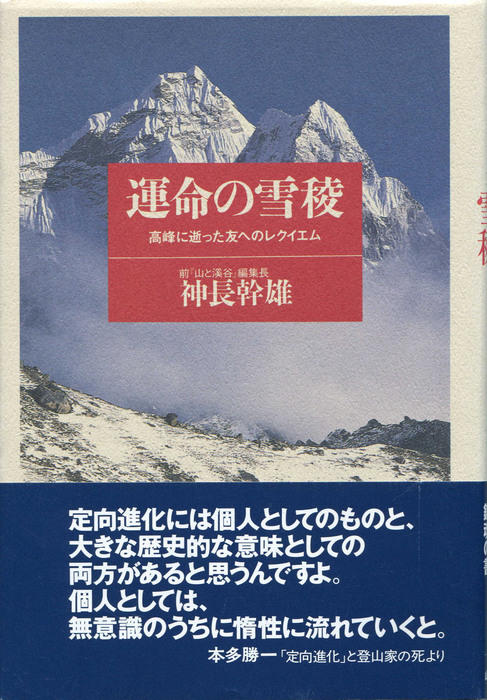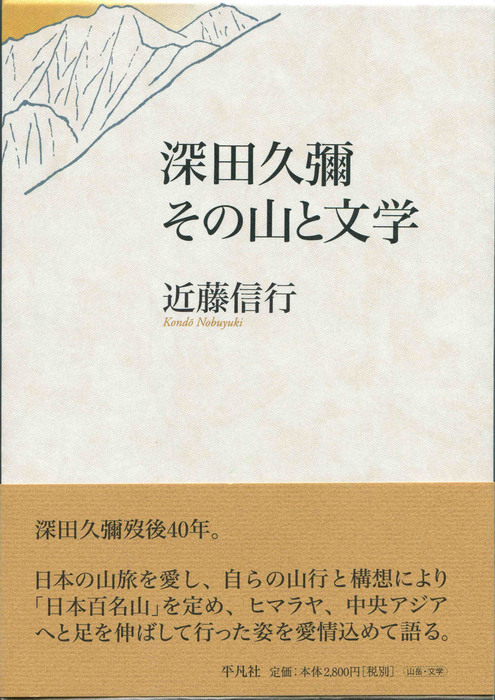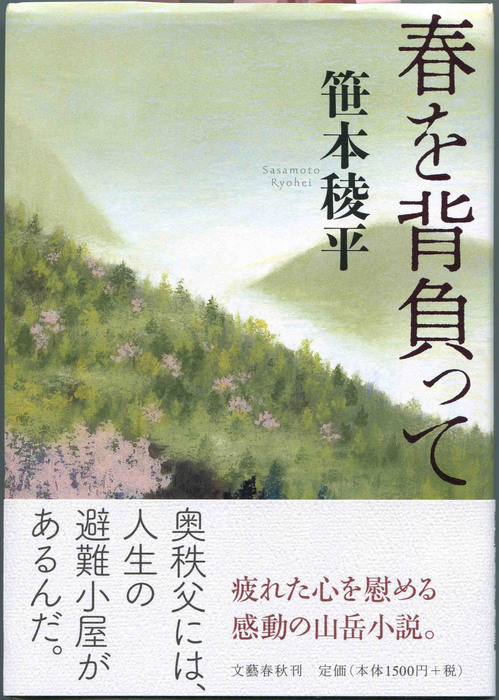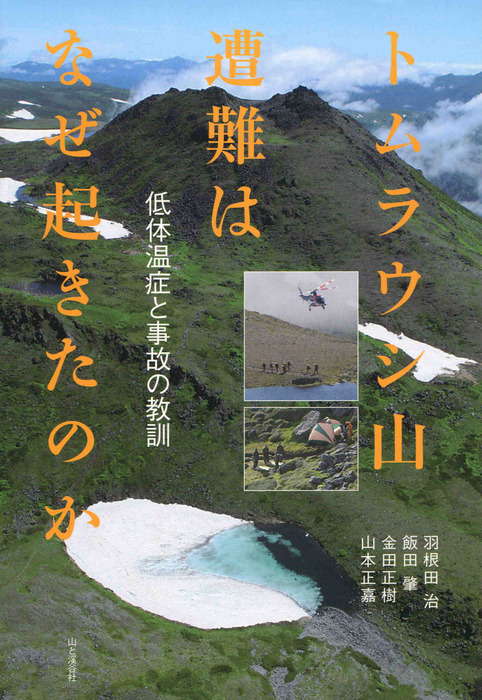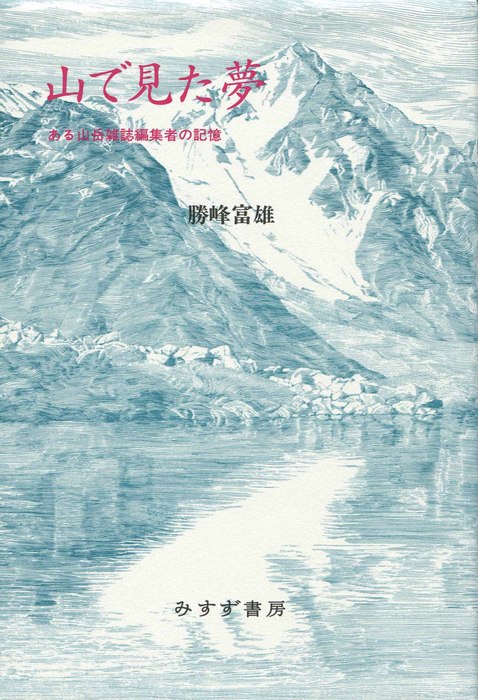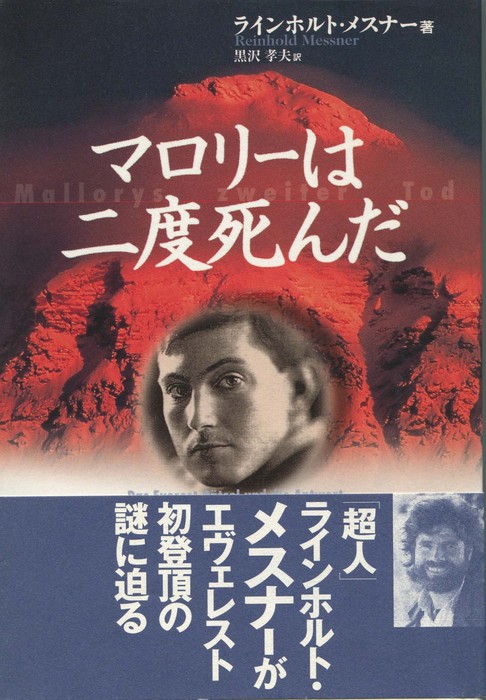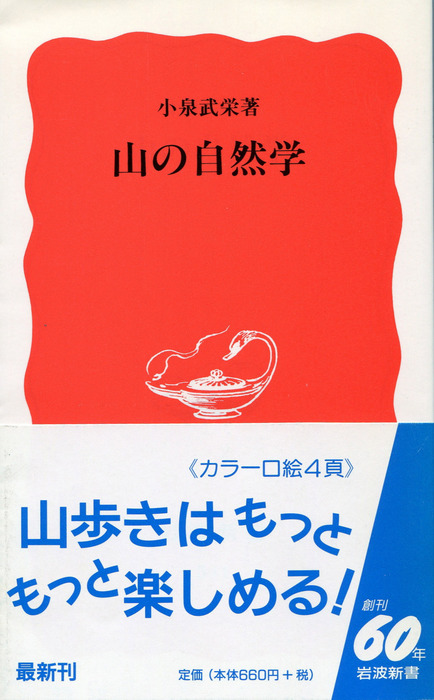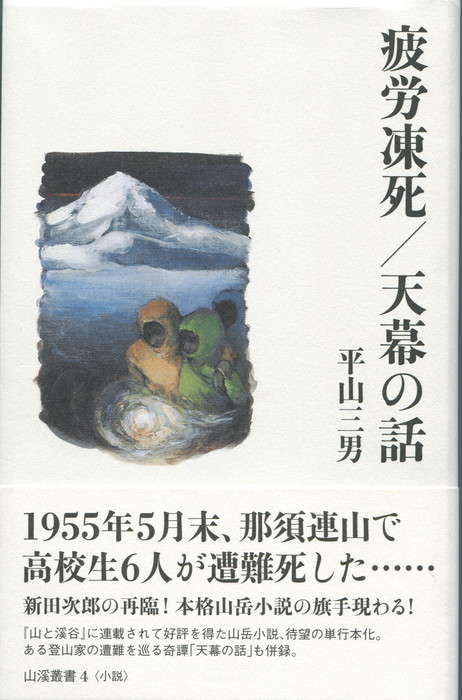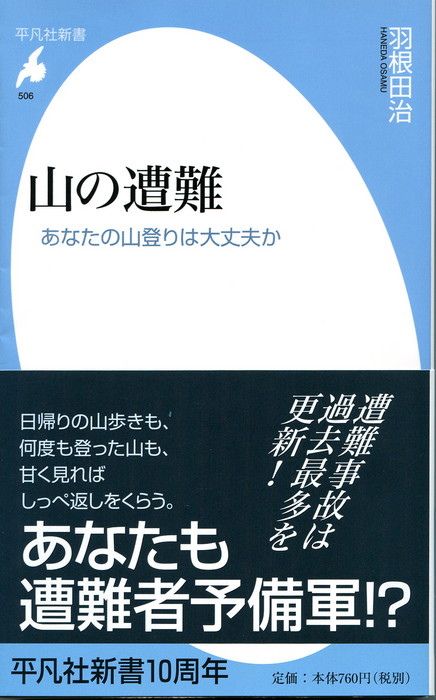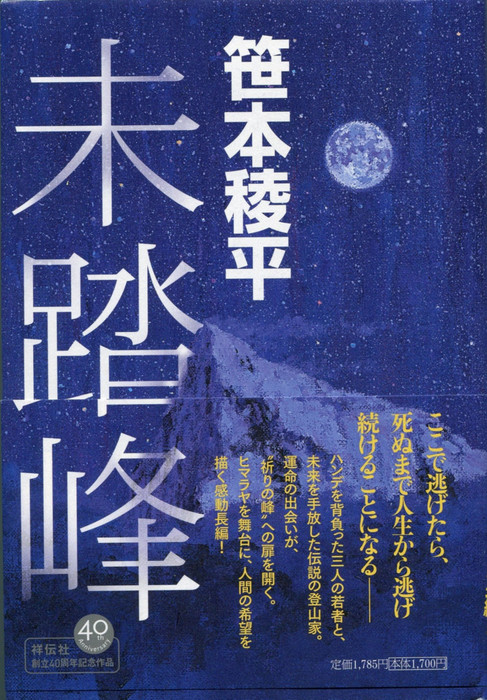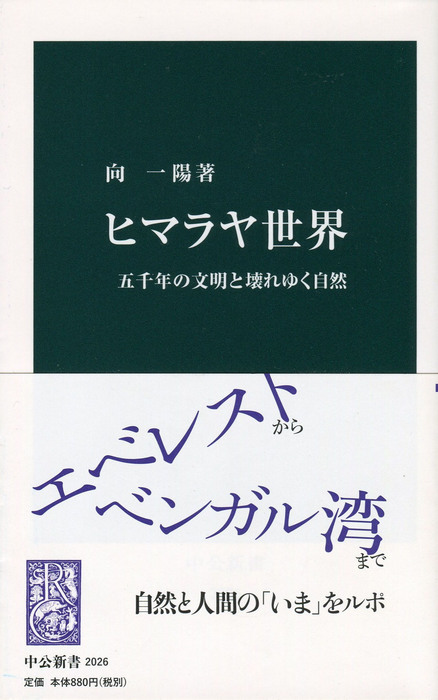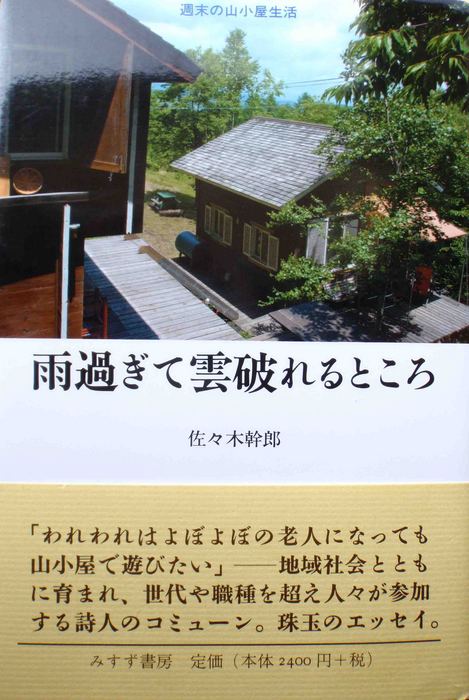人はなぜ秘境に向かうか~山の図書館 [山の図書館・映画館]
人はなぜ秘境に向かうか~山の図書館
◇「定本 日本の秘境」岡田喜秋著◇
著者・岡田喜秋は1947年に大学卒業後、日本交通公社に入り、1959年から12年間、雑誌「旅」編集長を務めた。その際、全国の秘境を訪ね歩き、紀行文を発表。それらをまとめて1960年に上梓した。その一冊が、半世紀を経て再編集、刊行された。
したがって、秘境取材が行われたのはほぼ昭和30年代前半(1955~1960年)になる。もっとも、著者自身があとがきで記しているところによれば、「旅」編集員になった1949年ごろから取材はしていたらしい。正確には執筆作業が昭和30年代前半ということになる。
なぜ、この本の取材・執筆時期にこだわるかといえば、ちょうどそのころが60年安保後、「所得倍増」を池田勇人内閣が掲げ、日本が高度経済成長、経済大国への道を歩み始めたころにあたるからである。都市だけでなく、地方や中山間地では古い民家が取り壊され、安っぽいつくりのプレハブ住宅が続々と建ち始める。そんな時期に、道さえおぼつかない山中や渓谷をほっつき歩いた人物がいて、好奇心あふれる読み物をものしていたのである。
「山」「谷」「湯」「岬」「海」「湖」の6大テーマに沿って、それぞれ三つの紀行文、計18編が収められている。
個人的な関心もあって、テーマとしては「山」が一番面白い。特に、マムシの恐怖におびえつつ、道らしい道もない山稜を行く「乳頭山から裏岩手へ―秘話ある山越え―」は秀逸で、著者の心細さがひしひしと伝わる。そして、たどりついた山中の温泉宿は雫石からざっと八里、冬はバスの終点から歩いても、とても一日ではたどり着けない難所である。そこを管理する若夫婦の思いに触れた個所などは、とても心が痛む。しかし、著者がさりげなく書くように「彼女は今年も冬を越すのである」。
さらに山路をすすむ著者は、ある峠で武骨なまでに頑丈そうな無人小屋を発見する。「利用者の少ないこんな峠道に山小屋を建てるなどということは、戦後の世知辛い人情からは生まれない。そんなところに、私は南部の人々の心根をよみとった」と著者は書き、「最後の下り」を「快い」気分で下っていく。
八甲田山での、あるスキーヤーの遭難を機に、冬場の雪上車による運行をやめてしまった温泉宿の主人の思いをつづった「酸ケ湯の三十年―冬の秘話―」も味わい深い。この章を、著者はこう閉じている。
――酸ケ湯の三十年は日本の風土の特殊性と、貧しい政治感覚と人間の軽薄さについて多くの教訓を秘めている。
ところどころに挟まれた、鮮明とは言い難いモノクロ写真とともに、滋味あふれる文章が心にしみる一冊である。消えゆくものへの郷愁ではない、時代に対する視点と批評が、文章に込められている。だから読み終えて、高度経済成長の初期に著されたこの書が、今という時代に重みを持ち始めていることに、どうしても思いをはせてしまう。
あらかじめ整備されて快適な温泉地や山間の宿をわれわれは求めがちだが、著者はそんなものにはおそらく目もくれず、全国の温泉を訪ね歩いた結果、温泉の最初の発見者は蛇、鶴、猿、熊などであった、と書く。その筆さばきには、まぎれもなく自然への畏敬が籠っている。
◇
「定本 日本の秘境」はヤマケイ文庫、950円(税別)。初版第1刷は2014年2月。これまで東京創元社(60年)、角川文庫(64年)、スキージャーナル(76年)で刊行された。
探検家であり、作家であるということ~角幡唯介の講演を聞く [山の図書館・映画館]
探検家であり、作家であるということ~角幡唯介の講演を聞く
「空白の五マイル」や「アグルーカの行方」の著作を持つ探検家・角幡唯介氏の講演(広島県山岳連盟主催)が10月4日、広島市内であった。強靭な肉体で次々と過酷な探検をこなすが、同時に惹かれるのは(こんな言い方をすると誤解されそうだが)、探検家〝らしからぬ〟生と死への深い洞察と、しかもその体験を重層的に文字に定着する、稀有な能力のためである。
講演は1時間余りで、「空白の五マイル」の原体験であるツアンポー峡谷探検のこと、そこからニューギニア探検(途中で挫折したらしい)をへて北極探検へと向かった経緯、そしていったんは、荻田泰永氏との1600㌔踏破=フランクリン隊が見た極北の風景=「アグルーカの行方」で結実した北極の雪原行に再び向かうことになった経緯などに及んだ。とてもこの時間枠に収まるわけはなく、最後は押せ押せになったが、それなりに面白くはあった。
彼は来年、グリーンランドのシオラパルクを出発点に北極圏を1200㌔~1300㌔踏破するという。3月には現地へ行き、夏に食糧をデポ、冬の北極圏を歩く。その際のキーワードとして三つをあげた。一つは「極夜」。終日夜であるとはどういうことか、体験したい。一つは「単独」。「空白の五マイル」でも、彼は単独行であることで生と死を見つめるという得難い経験を手に入れている。「自然との没入感」と語るが、この思想は彼の一連の作品に濃い縁取りを与えている。そして「犬を連れていく」―。理由を雄弁には語らなかったが、単独行による閉鎖された思考サイクルに陥らないための「保険」であるように見えた。
北極圏の氷床は、いうまでもなく何もない平らな雪原であり、地図とコンパスによる位置確定は困難である。しかし、現代にはGPSがある。にもかかわらず、今度の北極行では、GPSではなく六分儀を使って位置を割り出すという。星の位置を測り、そこから現在地を確定する。なぜそんなことをするのか。「冒険とはナビゲーションが面白いのであり、GPSにはその醍醐味がない」と彼は話した。「それでは極地の外にいる感じになる」―。ここに彼の冒険・探検への哲学がのぞいている。
もう一つ、講演の中で「犬との対話」に多くの時間を割いた。しかし、それは人間と犬の愛情物語でなく「格闘談」である。あるのは、愛玩動物としての犬ではなく過酷な環境の中での人間と犬の関係のありようである(こうした関係は、たしか本多勝一氏も、エスキモーのルポの中で触れていた)。生と死が極限的に問われる中で、人間と動物の命のやり取りがどうとらえられるべきかについては、「アグルーカの行方」にも麝香牛を殺す印象的な場面がある。
冒険や探検について「スポーツ的な部分が思考に合わない」と語る角幡氏の言葉は、まぎれもなく肉体(=探検家)と精神(=ライター)という二つの得難い能力を手に入れているかに見えた。

空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む (集英社文庫)
- 作者: 角幡 唯介
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2012/09/20
- メディア: 文庫

アグルーカの行方 129人全員死亡、フランクリン隊が見た北極 (集英社文庫)
- 作者: 角幡 唯介
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2014/09/19
- メディア: 文庫
山が主役と思えば楽しめます~映画「春を背負って」 [山の図書館・映画館]
山が主役と思えば楽しめます~映画「春を背負って」
原作は笹本稜平。彼にしては、作品の舞台を高山ではなく身近な低山、奥秩父に求めている。もちろんそこには彼流の計算があり、壮絶な山岳風景を硬質な文章で表すことで作品の重量を出すのではなく、人間の情の通いあいの部分でドラマの重量を出そうとしていたと思われる。主役はあくまで人間で、山は脇役であった。
しかし、映画では山岳と人間ドラマの位置関係ががらりと変わっている。もちろん、それは善し悪しの話ではなく、文字媒体と映像媒体の違いを考えてのことだろう。
監督は山岳撮影で定評のある木村大作。2009年の「剱岳 点の記」も、新田次郎のしっかりとした原作がありながら、主役は剱岳そのものだった。
外資系会社(と思われる)のトレーダーだった長峯亨(松山ケンイチ)が、山小屋を営む父(小林薫)の突然の死に直面し、会社を辞めて小屋を引き継ぐところから始まる。そこに、かつて父に助けられ小屋に住みついた高澤愛(蒼井優)や、大学の山岳部で父の後輩だったゴロさん(豊川悦司)、そして亨の母・菫(壇ふみ)らが絡み、亨もなんとか山小屋の主人らしくなっていく…。映画「春を背負って」は、ざっとこんなストーリーである。亨が、転身にあたってほとんど葛藤を見せないこと、その後も、ほぼ順風満帆であることなど、ドラマ的な奥行きはない。
しかし、それでいいのだろうとも思う。これだけの大自然を見せられた時、人間の存在や感情の起伏が織りなすドラマなど、あまりにもちっぽけだからだ。
要は、山小屋の周辺に広がる四季折々の山岳風景を楽しめばいい、そんな映画である。原作の後景にあった奥秩父が立山連峰・大汝山に置き換えられた時点で、例えば「山での死」を常に介在させながら人情話を重ねていく、といった原作の色彩は望むべくもないのだが、逆に言えば、これほど単色で一直線のストーリーだからこそ、3000㍍級の山々の雄大な景色が我々を楽しませてくれる、ということであろう。
何かが違った~山の図書館 [山の図書館・映画館]
何かが違った~山の図書館
「世界最悪の旅 スコット南極探検隊」(チェリー・ガラード著)
ノルウェー人のアムンゼンが南極の極点に到達したのは1911年12月14日だった。それより約1カ月遅れの翌年1月17日、英国人スコットが極点に到達。しかし、二つの旅は鮮烈に明暗を分ける。アムンゼンが無事に帰還したのに対して、スコット隊は極点からの帰途、5人全員が死亡する。
スコット隊のあまりに悲惨な旅を、探検隊の一員だったチェリー・ガラードが再現したのがこの一冊である。
1910年10月、メルボルン港に入ったテラ・ノバ号(スコット隊の乗船)に一通の電報が舞い込む。「余は南極に向かわんとす。アムンゼン」―。これがすべての歯車を狂わせる発端となる。その最初の動きは翌年2月、南極大陸に貯蔵所を建設したスコット隊が、目と鼻の先にアムンゼン隊の船を見つけたことに始まる。事実上、極点レースがスタートするが、むろん今日のような快適な環境ではない。ガラードは、その模様を描いている。気温はマイナス50度前後、進む距離は1日4㌔から5㌔。夕刻には凍った寝袋に潜り込む。そして「おそろしいけいれん」を起こす。事態は悪化し寝袋の中にいても凍傷を起こすようになる。
隊は4人ひと組で構成された。しかし、スコットは極点アタックチームを5人にした。1人でも多く連れて行こうと思ったのかもしれない。しかしこれも、歯車を狂わせる一因になる。食糧など物資の量、テントの数、ソリの大きさ、すべてがそれまでの計算と違ってくる。スコット隊の極点到達は12年1月17日。アムンゼン隊は既に1カ月前に到達を果たしている。ここからスコット隊の絶望的な帰還が始まる。そして3月27日には、全員がテント内で死に絶える。
ガラードが記す遭難隊発見の模様。
――ライト(注:隊員の一人)はまっすぐにこっちへやって来た。「テントだ」。(略)なにげない雪の荒地であった。
ガラードは続いて、隊員たちが残した日記を明らかにする。向かい風でソリは遅々として進まず、1日の行程はわずか数㌔。隊員は次々と凍傷で足をやられていく…。
何が違ったのだろうか。アムンゼン隊はまっすぐ極点に向かい、史上初めて到達し、ひとりの生命も失うことなく戻ってきた。スコット隊は多くの困難と闘い、多くの生命を失い、極点初到達の栄光も担うことがなかった。
ガラードは「アムンゼン隊が個人的資質が高かったと結論付けるのは早計」としたうえで、山のように「もしも」を連ねる。もしアタックが4人だったら、もしスコット隊が先に拠点に到達していたら、もし余分の燃料があったら…。しかし、事実は変わらない。
そしてこの一冊を、ガラードは次の言葉で結ぶ。
――探検とは知的情熱の肉体的表現である。
◇
「世界最悪の旅」は中公文庫、838円(税別)。初版第1刷は2002年。チェリー・ガラードは1886年、オックスフォード生まれ。スコットを隊長とするイギリス南極探検隊に動物学者として参加し、帰還を果たす。1959年没。
「百年前の山を旅する」(服部文祥著) [山の図書館・映画館]
「百年前の山を旅する」(服部文祥著)
著者は山岳雑誌「岳人」編集部に所属しながらK2登頂など、いわゆる先鋭的な「登山」を経験。その後、装備を切り詰め、食糧もテントも持たず山に入る「サバイバル登山」を始めた。なぜか。その動機の部分が、この一冊に込められている。
「序」にあたる「過去とシンクロする未来」から。
――登山とは、あるがままの大自然に自分から進入していき、そのままの環境に身をさらしたうえで、目標の山に登り、帰ってくることだ。自分の力ではできないことを、自らを高めることなしに、テクノロジーで解決してしまったらそれは体験ではない。(略)だから登山者はできる限り生身であるほうがいい。昔の山人のように――。
現代の登山者である我々は、雨が降ればゴアテックスの雨着を着る。ガスコンロを使えば、即席で胃袋を満たせる食糧もある。暗くなれば周囲を照らすヘッドランプもある。軽量で快適なテントやシュラフもある。これらが進歩すればするほど、山の闇や天候不順、食糧が手に入れられなかった結果としての空腹感、それらがもたらす恐怖と距離を置くことができる。それでいいのだろうか。山はきちんと畏怖すべき存在ではないか。そうでなければ山と向き合ったことにならないのではないか。そう言っている。
1909年、田辺重治と小暮理太郎が高尾から奥多摩へと縦走した。日本での縦走の記録としては最も古いものだという。「天幕も寝具もリュックも水筒もなく、肩掛け鞄に米と佃煮とナベだけを入れ」、現代の感覚からすれば「無謀登山」とも思える山行を服部は実行する。
「私達の辿っている尾根が、やがては三頭山に連なることが進むにつれ明らかになった」―。
100年前のこの記述に、著者は「しびれた」と書く。地図が一般に手に入るようになったのは1913年。二人は地図も持たず縦走に挑んだのだ。このように、ほぼ徒手空拳で山に挑んだ昔の人たちは肉体的、精神的に強かったのだろうか。服部の見方は少し違う。
――肉体的なちがいではなく、その肉体をどう使うのかという世界観が現代と100年前とは根本的に違うのだ。
たとえば二人は奥多摩から青梅まで半日で歩き、帰京している。現代人なら苦痛だろう。しかしそれは、単に鉄道が青梅までしか通っていなかったからではないか。彼らにとっては当たり前だっただけで「強さ」とは関係ないと言う。ただ、文明の利器に頼る我々の山行と、自力だけを頼って山に入る彼らと、どちらが自由だろうか、というのが著者の根本的な問いかけである。
この一貫した問いのもとに、1915年の笛吹川遡行(「日本に沢登りが生まれた日」)、1912年のウェストン、上條嘉門次らの奥穂高岳南稜登攀(「ウェストンの初登攀をたどる」)などが追体験される。
解説は角幡唯介。「人はなぜ山に登るのか。(略)この解答困難な謎にあえて正面切って挑み、その答えにかなり肉薄している数少ない登山家」としたうえで「(服部が)現代登山の枠組みの外側に飛び出すことを選択」することで、我々は「現代社会の表裏をあぶり出す、きわめてすぐれた文明批評」を手に入れたと指摘する。
「百年前の山を旅する」は新潮文庫。初版第1刷は2014年1月1日。630円(税別)。著者は1969年神奈川県生まれ。96年から「岳人」編集部。著書に「サバイバル登山家」など。
「山に入る日 山野彷徨から瞑想的登山へ」(細田弘著) [山の図書館・映画館]
「山に入る日 山野彷徨から瞑想的登山へ」(細田弘著)
最近、相次いで山ヤの本を読んだ。一冊は「初代 竹内洋岳に聞く」(塩野米松著)で、もう一冊が、この「山に入る日」である。率直に言って「竹内―」は期待外れであった。むろん、竹内は世界8000㍍峰14座を、日本人として初めて完全登頂した登山界の超人である。しかし、この本には、山をめぐる複雑でほとばしるような思いも、同じく8000㍍峰を完全登頂したラインホルト・メスナーのような晩年の諦念めいた想念もない。
例えば、竹内は山の魅力についてこう語っている。「何が面白いのって?(略)全体から言えば、限りなく魅力的で、面白いものですよ」。これだけである。インタビュアーの腕もあるのだろうが、やはり物足りない。
「山に入る日」の著者・細田は、竹内とは正反対の登山者である。奥付の経歴を見ると、高校時代から登山を始め、若いころは岩もやったらしい。30歳前後の6年間は、世界を放浪したとある。そして50歳を過ぎての登山再開。この書では、いわゆる名の通った高山はほとんど登場しない。2000㍍に満たない山々で、時にみじめに敗退する齢60を過ぎた単独登山者の思いがつづってある。その中で、岩壁を颯爽と登り尾根の風に吹かれながら疾走するだけが登山の魅力ではないと著者は繰り返し語っている。
――私の年齢では何日で歩くかではなく、歩き通すこと自体が目的になる。(大峰山奥駈け日記)
そして、
――体力のある順に四人がばらけた。私は三番手である。
となる。「四人」は、たまたま山でであった間柄である。この文の最後は、こう締めくくってある。
――おそらく熊野奥駈道を歩ききることの意味(意義)は、この風を体感することにある。
書の全体は、第1章で単独登山の魅力、第2章で山をめぐる瞑想、第3章で、やや本格的な山行記、となっている。第2章、表題になった「山に入る日」は、なかなか魅力的な書き出しである。
――ザックを背にして山に向かう特急列車に乗るとき、後ろめたいような、こそばゆいような微かな快感を覚える。そして、(略)ゆっくり背凭れに身を委ねながら、じんわり湧いてくる解放感に浸る。
だれもが味わった感覚ではないだろうか。そして、
――気分転換なら小さな山がいい。でも心に重荷があるならば、大きな山のほうがいい。それだけ多くの汗を流す必要があるからだ。
著者はここに、旅と登山の違いを見いだす。旅には、登山のような充足感や心の澱のようなものを昇華する力はない、という。この章で面白いのは「兵法者と登山者」という文章である。登山という行為は、剣豪小説に出てくる兵法者の心根に酷似している、と著者は言う。そのうえで「新説 佐々木小次郎」(五味康祐)を引く。
――兵法者が負けるを覚悟で仕合に臨むことは断じてない。(略)同様に勝つと分かって仕合にのぞむことも、ない。(略)勝つとも負けるとも予測しがたい或る不可知なものを相互の剣理に感じとった時、はじめてその不可知に生命をかけて仕合をするのである。
分かる気がする。
第3部では、「西海谷三山縦走記」がとび抜けて面白い。新潟・雨飾山の北方に連なる魁偉な山々。1500㍍ほどの山並みが、著者の心をわしづかみにする。一度の撤退の後、ある年の10月下旬に雨飾へと向かう。三山の最初の鋸岳手前で山座同定をしたら、鋸岳と思ったのは、実は鉢山と分かる。鬼ケ面山と思ったのは阿彌陀山だった。しかし、なんとおどろおどろしい山名の連なり。
風雨の吹きすさぶ尾根にテントを張って沈殿し、痩せた水平路を行き、切戸(キレット)を抜けて岩壁に取り付き、ずり落ち、それでも登り切る。こんなシーンが続く。
決して成功の物語ばかりでない。断念に次ぐ断念。「遥かなる剱岳北方稜線」もそうした文章である。時に、遭難の危険性にさえ直面する。だがその果てに、著者はたどり着いたキャンプ場のベンチで、足元に落ちた蝉と蟻の行列を見ている。そんな心境になりたいものだ。
「山に入る日」は白山書房、1800円(税別)。初版第1刷は2013年10月1日。著者の細田弘は1946年生まれ。高校卒業と同時に秀峰登高会。奥多摩で宙づり事故にあい単独行に。世界74カ国を放浪した後、51歳から山旅登山を再開した。著書に「夢想の峯々」。
極地をトレースする豊饒な文体~山の図書館 [山の図書館・映画館]
極地をトレースする豊饒な文体~山の図書館
「アグルーカの行方」(角幡唯介著)
世界地図を広げてみる。ヨーロッパからアジアへと向かう航路を探す。アフリカ大陸西岸を南下して喜望峰を回るか。地中海を東進して中東を通過するか。南米大陸の東を通り、マゼラン海峡を抜けるか。しかし、15世紀から17世紀にかけての大航海時代を経て、それらはスペイン、ポルトガルが押さえていた。遅れてきた大国イギリスはそこで、北極海の通過をめざす。19世紀に始まった北西航路探検である。ヨーロッパから北西を目指して、氷の海に乗り出す。しかし、その探検史を見るといずれも2~3年の期間を要している。発達途上にあった内燃機関による小さな船と、保存技術が確立されていない膨大な食糧。20世紀初頭にアムンゼンが完全航海するまで、その探検史には悲惨な事実が詰まっている。
21世紀に入ってなお地図上の空白地帯が存在することを知らされたのは「空白の五マイル」を読んでであった。世界最大の規模と言われるチベットのツアンポー峡谷。著者の角幡唯介は20代から30代初めにかけ、この地に3度踏み込む。そして探検へと向かう中国での長い列車の旅で、角幡が手にした1冊の本は「世界最悪の旅」だった―。
アムンゼンと、南極点初到達を争って敗れた英国ロバート・スコットの探検記だ。スコットら5人は失意の中で基地に戻る途中、極寒のブリザードにのまれて落命する。アプスレイ・チェリー=ガラードの筆になる探検文学の古典は、角幡の心に何かを植え付けたにちがいない。この時から13年後、角幡は「極地」へと向かう準備を始めている。
北西航路探検の歴史の中でも、とりわけ悲惨だったのは1845年から48年にかけての、ジョン・フランクリンの一行であろう。氷に閉ざされ、絶望的な飢餓の中で129人全員が死亡したと伝えられる。角幡は、知人で北極探検家である荻田泰永とともに、このフランクリン隊のルートを追って103日間1600㌔を歩きとおす。
――ただ、ホールの集めた証言が、根拠が薄いと簡単に切って捨てることができるようなものではないという気もしていた。だから思ったのだ。だとしたら、行ってみるべきなのではないだろうか。
ホールとは、フランクリン隊が行方不明になって15年後、なお隊のメンバーの生存を信じてイヌイットから証言を集めた探検家である。これに対して否定的な見解を示したのは、歴史学者のリチャード・サイリアクス。しかし、ホールが集めた証言の中で、次のような表現が角幡の心をとらえる。
最後にアグルーカと二人の仲間は不毛地帯に向けて旅立った。
彼もまた、その風景の中を旅したいと思う。アグルーカとは、イヌイットの言葉で「大股で歩く男」。背が高く、果断な性格の人物に付けられることが多い。必ずしも、特定の人物を指すものではないが、イヌイットに語り継がれるアグルーカは、果たしてフランクリンか、あるいはフランクリンの死後に隊を率いたクロージャーを指すのだろうか。ここで、一つの事実が交錯する。フランクリンが遭難したころ、時期的にも地域的にも最も近くで活動していた探検家ジョン・レーが「アグルーカとは自分のことである」と、ある新聞で発表するのである。
フランクリン隊が体験したであろう飢餓の果てのカニバリズム、雪原の麝香牛母子と角幡、荻田の生と死のドラマ、荒涼たる風景を行く3人の男―彼らの一人はまぎれもなく「アグルーカ」と呼ばれた―の、謎に満ちた行方。「空白の五マイル」から、さらに豊饒さを増した角幡の文体が、不毛の極地をトレースする。
「アグルーカの行方」は集英社刊。1800円(税別)。初版第1刷は2012年9月30日。角幡唯介(かくはた・ゆうすけ)は1976年、北海道芦別市生まれ。早大政経学部卒。2002~2003年にチベット・ツアンポー峡谷の未踏査部を探検。朝日新聞記者を経て10年「空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む」(集英社)で第8回開高健ノンフィクション賞、11年に第42回大宅壮一ノンフィクション賞、第1回梅棹忠夫・山と探検文学賞。次作の「雪男は向こうからやって来た」(集英社)は12年、第31回新田次郎文学賞。
北アの黎明期を生きた歌人~山の図書館 [山の図書館・映画館]
北アの黎明期を生きた歌人~山の図書館
「山を想えば人恋し」石原きくよ著
副題に「北アルプス開拓の先駆者・百瀬慎太郎の生涯」とある。慎太郎は信濃大町の老舗旅館の息子として生まれ、歌人にして登山家。しかし、彼のつくる短歌は素直そのもので、むしろ次のフレーズでよく知られている。一度は耳にしたことがあるだろう。
山を想えば人恋し
人を想えば山恋し
今で言えばキャッチコピーである。
慎太郎が旅館「対山館」の跡取りとして生まれたのは1892年、今から120年ほど前のことである。この年、日本の山を世界に紹介したウォルター・ウェストンが槍ヶ岳に登頂。翌93年には対山館に宿泊、針ノ木岳を目指している。この年にはウェストンの前穂高登頂に上條嘉門次が同行。二人の交友がその後、語り継がれる。慎太郎は、文字通り北アルプスの黎明期に生まれたといえよう。
中学を卒業した慎太郎は、家業を継ぐ。そのころつくった歌がある。
雪の嶺に吹きつけられし雪あまたにごりて暗き高原の街
鬱勃とした心情が込められている。そんな彼が、人が変わったように仕事熱心になる時があったという。山を目指す人たちが宿を求めて来た時である。このころ、慎太郎は忘れられない経験をする。針ノ木峠から黒部谷を経て立山へと抜ける山行である。案内人は遠山里吉。通り名は品右衛門。針ノ木近辺に関しては嘉門次さえ一目置く存在であったという。1910年10月、町は秋の盛りだが、峠は初冬の荒涼とした風景だったと著者・石原は書いている。
13年夏、槍ヶ岳から上高地に降りた21歳の慎太郎は島々の旅館でウェストンと出会う。この偶然をきっかけに、二人は親交を深める。第一次大戦が始まった14年にウェストンは対山館を訪れる。英国への帰国を決意し、日本の山々に別れを告げる旅の第一歩として針ノ木峠を訪れるためであったという。ウェストンは15年、日本を離れる。
慎太郎は17年に大町登山案内者組合を結成する。日本で初めての山岳案内人の組合である。そろいの法被には「日本アルプス」の文字が染め抜かれた。ウェストンがヨーロッパに紹介し、登山家で文筆家の小島烏水が国内で定着させた名称である。当時の慎太郎は烏水に心酔していたようだ。案内者組合の結成も、烏水に触発されてのことである。
そのうち、国内にスキーが普及し始めると、冬季北アルプスに関心が向き始める。23年3月、富山から針ノ木峠を越え大町に抜ける慎太郎らの山行は記録映画として撮影され、社会的なニュースになる。それにつれて冬山を目指す人たちが増え、避難小屋を求める声が、登山者たちから高まる。慎太郎が針ノ木雪渓と扇沢の間に大沢小屋の建設を決めたのもこのころである。赤字覚悟であったという。
27年12月大みそか、早大山岳部の遭難事故が起き雪崩で4人が生き埋めになった。捜索態勢づくりは進まず、対山館が捜索隊を出し捜索本部となった。遺体が見つかったのは翌年5月だった。しかし、この遭難事故で避難拠点としての大沢小屋の価値が再認識された。慎太郎の手によって雪渓の上部に針ノ木小屋ができたのは、1930年のことである。
著者は北アルプス黎明期に深くかかわった人物として上條嘉門次、百瀬慎太郎を挙げている。おそらくこの二人の間にいるのが、日本アルプスを世界に知らしめたウォルター・ウェストンだろう。信州と越中を結ぶ要路として古くから知られてはいたが難所のゆえに越える人の少なかった針ノ木峠を、今日のように魅力的なアルペンルートにしたのは百瀬慎太郎の功績である。しかし、その足跡を追った著書はほとんどない。石原きくよのこの書は、貴重な1冊といえる。
| 著者石原きくよは大町市在住、日本児童文学者協会所属。「山を想えば人恋し」は郷土出版社(松本市)刊。1600円(税別)。初版第1刷は1998年。 |
生と死の分水嶺を描く~山の図書館 [山の図書館・映画館]
生と死の分水嶺を描く~山の図書館
「運命の雪稜 高峰に逝った友へのレクイエム」神長幹雄著
1000㍍に満たない、ある低山での体験だ。頂上から、登ってきた道を下りようとした。そのルートの横には巨木の陰にもう一本のルートが、あたかも山裾まで続くかのように口を開けていた。のぞいてみると、道幅は案外と広い。ここを下ってみるか。たいした考えもなく足を踏み出した。しばらくは快適だった。落葉樹林をすり抜けていく。しかし、踏み跡はどんどん薄くなり、ついに杉の倒木が行く手を阻んだ。なおもそれを乗り越えると、前方は崖だった。もう引き返すしかなかった。来た道を登りはじめた―。そのつもりだった。しかし、それは来た道ではなかった。ひとり山中で方角を見失ってしまった。途方に暮れていると、幸運にも1人の登山者と出会った。位置を聞くと、なんと下山ではなく隣の山へと向かっていた。もしあのとき、登山者と出会わなかったら―。
「運命の雪稜」の巻末には、著者と本多勝一の対談が収録されている。この中で本多は、困難さを追求するアルパイン登山のありように対して「比喩としての『定向進化』」という視点を示している。これに著者は「ここ20年ほどの遭難は(略)ある種の慣れから危険予知能力が鈍くなる可能性を示唆している」と応じている。簡単に言えば「油断」だが、そう言ってしまえないところがある。「魔が差す」とでも言うのだろうか。
8000㍍地帯は、死のにおいがするという。酸素濃度は地上の3分の1。そこへ意識的に足を踏み入れる。著者によれば「死と紙一重の世界」である。だれも、死にたくはない。しかし、死にたくはないという動機だけで行動すれば、こうした高山に足を踏み入れることなど永遠にない。「死」という一線を越えて、命を賭してまでそこへ向かう何かがあるはずなのである。
鍛えられた理性でなお支配できぬ一瞬の心のすきと、抑えきれぬ情熱が織りなす結末。この二つの軸が作り出す八つのドラマが、この書を構成している。
ナンガ・パルバットの頂上直下。中島修は高度順化の失敗からか体調を極度に悪化させていた。それを押して、一度はあきらめかけた一歩を踏み出す。永遠に戻ることのできない一歩を=「不条理の頂上台座」。
高見和成は厳冬の大山頂上から滑落する。奇跡的に死を免れ、3日間かけて8㌔の下山を決行する。その5年後、高見は冬の大山であっけない死を迎える=「地獄谷からの生還」。
トゥインズ主峰を狙って、佐藤正倫ら7人は快晴の雪原にトレースを刻んだ。セカンドとしてアンザイレンしていた佐藤はトップを代わるためザイルを外し、トップのすぐ後ろに着く。小さな声とともに佐藤の姿が消えたのは一瞬だった=「悔恨のヒドゥンクレバス」。
運命のわずかな分水嶺が、生き残るものと死んでいくものを作り出す。しかし、山で死ぬ者はまだいいのかもしれない。各章ではその死を受け止め、受け入れようとする家族の姿が描き出される。中島の父は葬儀のあいさつでこう述べたという。
――正倫が情熱のすべてをつぎこんだ山を、私はこれから年月をかけて理解していこうと思っています。それが、正倫のなによりの供養になるのではないでしょうか。
わたしたちのような低山徘徊者は特に、山で死んではいけませんね。
「運命の雪稜 高峰に逝った友へのレクイエム」は山と渓谷社刊。1500円(税別)。初版第1刷は2000年1月10日。神長幹雄は1950年東京生まれ。信州大卒業後、山と渓谷社入社。94年から「山と渓谷」編集長。
人生観を山に重ねた文学者の相貌~山の図書館 [山の図書館・映画館]
人生観を山に重ねた文学者の相貌~山の図書館
「深田久彌 その山と文学」近藤信行著
近ごろ珍しい箱入り本である。このこと一つとっても、深田久彌に対する愛着が分かる。著者は文芸評論家であり、深田の二つの著作集に携わったと自らあとがきで書いている。一つは「山の文学全集」、一つは「山の文庫」。ともに朝日新聞社から刊行された。その著者が折々に触れた深田の「山と文学」、それに「山の文学全集」の解説を編んでこの一冊が生まれた。
したがって、著者自身が明かしているように、やや雑多な寄せ集めの感がないでもない。その中で畢竟の文章は冒頭「深田久彌・その山と文学」で、深田文学への慈愛に満ちた視線であふれている。それは深田の終焉の地、茅ケ岳の描写から始まる。没後10年の1981年春、山麓に建てられた記念碑には次の言葉が刻まれているという(有名な言葉だが、私自身はまだ目にしていない)。
百の頂に
百の喜びあり
私などは「一つの頂に百の喜び」があると思っている方だから、この言葉の深みはとてもよく分かる。そして彼は、山への情熱を次のようにも書いている。
「結局私の山登りは、高村光太郎のように、
山へ行き、何をしてくる、山へ行き、
みしみし歩き、水飲んでくる
それだけが全部であったようだ。せめては、私は山のような人間にならねばならぬ。山のような文章が書けるようにならねばならぬ」
山のような人間にならねばならぬ―。
この一念で、深田は膨大な、山のような文章を「みしみしと」残したのだろうか。
思うのは、深田の文学者としての相貌である。彼は作家だったのか、批評家だったのか、それとも文献史家だったのか。小説家としての彼は「津軽の野づら」一連の作品で鮮烈なデビューを飾っている。しかしその後、成立過程について「揣摩臆測」がなされ、私生活の転換とともに作品は変質していく。遠回しな言い方だが、つまりは妻・北畠八穂との「合作」問題である。近藤が「(深田は、生地である)大聖寺では聖人のように扱われているが、青森に行くと泥棒呼ばわりである」と書いているように、一方で「盗作」疑惑が消えない。この説をとる代表例が北畠と同郷人である田澤拓也の「百名山の人 深田久彌伝」であろう。
しかし、近藤はここで「八穂は自分の筆ではひとり立ちできなかったのではないか」との見方を示し「発表は合意のもとになされたにちがいない」としている。つまり、深田の初期の文学作品は編集者としての深田と文学の才あるいはきらめきを持つ八穂との共同財産、というわけだが、深田は20年ぶりにある女性と運命の出会いを果たすことで八穂との生活に終止符を打ち「二人のかけがえのない財産」はもろくも崩れ去る。近藤はここに「作品の不幸」を見ている。
果たして田澤と近藤のどちらの視線が真実を射ぬいているか、今となっては判別できることではないが、少なくとも近藤の視線が深田への慈愛に満ちていることは分かる。
そのうえで近藤が、小林秀雄とも親交の深かった深田について「批評家」であるとの見方を示している点がとても興味深い。例えば「百名山」についての近藤の解説。百名山の選定基準として「山の品格、山の歴史、山の個性」をあげ「山の品格という点についていえば、深田久彌はしばしば山を人間化して眺めてきた」と書く。人生観照の視点である。小林が数々の文学作品に己の人生観を投影したように、山を通して自らを語る批評家・深田久彌を、近藤は見ている。
小林秀雄と深田久彌の文学者としての立ち姿の同一性、とでも言えばいいだろうか。
「深田久彌 その大和文学」は平凡社刊。2800円(税別)。初版第1刷は2011年12月16日。著者の近藤信行は1931年生まれ。山梨県立文学館館長。著書「小島烏水―山の風流使者伝」のほか、編著として志賀重昂「日本風景論」などがある。
人生の滋味あふれる6編~山の図書館 [山の図書館・映画館]
人生の滋味あふれる6編~山の図書館
「春を背負って」笹本稜平著
針の木峠に小屋を建てたのは百瀬慎太郎である。昭和2年の暮れ、これも百瀬が建てた大沢小屋を拠点に早大山岳部員がスキー合宿をしていて雪崩に襲われ、4人が亡くなった。遺体は翌年6月に見つかった。この遭難をきっかけに百瀬は針の木小屋の建設を思い立ち、昭和5年に小屋が開かれた。
百瀬は大町の旅館「対山館」の息子として明治25年に生まれた。ウォルター・ウエストンが翌年、この「対山館」を訪れたという。歌人でもあった百瀬は後年「山を想えば人恋し 人を想えば山恋し」のフレーズを知人が広めたことで注目された。なかなかに味わいある人柄だったと伝えられるが、評伝は少ない。
笹本稜平は、いくつかの山岳小説をこれまでに書いている。たどってみると、面白いことに気づく。最初に手掛けたのは「天空の回廊」。舞台はエベレストである。2作目は「還るべき場所」。K2で恋人を失い、再びその峰に「還ってきた」男の物語だ。3作目ではヒマラヤのカンティ・ヒマール山域を舞台に、7000㍍弱の架空の美峰「ビンティ・チュリ」を若者3人が目指す。分かるだろうか。標高が徐々に下がっている。その分、人間の物語が色濃くなっている。
――その小屋は、甲武信ヶ岳と国師ヶ岳を結ぶ稜線のほぼ中間から長野側に少し下った沢の源頭にあった。
電子機器メーカーに勤める長嶺亨は、交通事故であっけなく死んだ父の、奥秩父にある山小屋を継ぐ。ふだんはホームレス生活を送り、ときおり小屋に顔を見せるゴロさんは父・勇夫と大学ワンゲルの先輩・後輩の間柄である。結局彼も、シーズン中は小屋に住みつく。父が撮ったシャクナゲの群生の写真を追ってこの山塊を訪れた若い美由紀もまた、小屋の生活に生きがいを見いだし始める。3人をめぐる人間模様を中心にストーリーが紡がれていく。
6編それぞれが水彩画のように淡いが、それぞれにしっかりと物語がある。沢で偶然見つけた白骨死体とそばに落ちていた高級時計が夫婦の哀歓を浮き彫りにする「野晒し」。事故に遭い生死の淵をさまよう夫に電源の切れた携帯で山から呼び掛ける「疑似好天」。「空を飛んできた」少女が垣間見せる大人の社会の愛憎―「荷揚げ日和」。しいて好みを言えば、前半まで怪談仕立てを思わせる「野晒し」がいい。
――前穂高へとせり上がる北尾根、怪異なジャンダルムの岩峰とそこから西穂高に至る鋸歯のような稜線、残雪の斑を残して優美な笠ヶ岳、その名の通り鋭利な三角錐を天に突き刺す槍ヶ岳。(「還るべき場所」)
こうした鋭角的な描写も悪くはないが、「春を背負って」では注意深く山の情景は避けられている。むしろ、山はそれぞれの心の中に息づいているのである。と、ここまで書けば、冒頭で百瀬慎太郎のフレーズを出した意味を分かってもらえるだろう。
難点は、女性の側が思いを寄せる、といった展開が多いことかもしれない。やっぱり男が書いた小説だね、と言われるかも。次作はぜひ、都会に住む人間たちがおりなす山岳小説を書いてほしいものです。
「春を背負って」は文藝春秋社刊。1500円(税別)。初版第1刷は2011年5月30日。笹本稜平は1951年、千葉県生まれ。2001年「時の渚」でサントリーミステリー大賞。2004年「太平洋の薔薇」で大藪春彦賞。警察小説、冒険小説でも知られる。「還るべき場所」は6月に文庫本化された。
わが身をも透過する強靭な「視力」~山の図書館 [山の図書館・映画館]
わが身をも透過する強靭な「視力」~山の図書館
「空白の5マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む」(角幡唯介)
いわゆる冒険ノンフィクションで印象に残るシーンを一つだけ挙げろ、と言われれば躊躇なくギャチュンカン頂上直下の山野井泰史を描いた沢木耕太郎「凍」を挙げる。それはなにより透徹していて美しい。
――そのとき、山野井は、妙子のことも忘れ、高みから自分を見ている眼そのものになっていた。自分が、たったひとりで、頂を目指している姿がはっきりと見えた。
――早く頂上にたどり着きたい。しかし、この甘美な時間が味わえるのなら、まだたどり着かなくてもいい。
――全身の感覚が全開され、研ぎ澄まされ、外界のすべてのものが一挙に体内に入ってくる。雪煙となって風に飛ばされる雪の粉の一粒一粒がはっきりと見えるようだった。いいな、俺はいい状態に入っているな、と思った。
たしかにここで山野井は「高みから自分を見ている眼」、言いかえれば「神の目」に近いものを得ているかのようだ。しかしこの作品、山野井と沢木という得がたい二つの才能がぶつかり合ってようやくできたものであろう。
「空白の5マイル」はチベット、ヒマラヤの麓にある「世界最大」の峡谷に踏みいった男の記録である。西暦2000年を過ぎてなお、まともな地図さえない人跡未踏の谷があるなどとは驚きだが、その地に単独で向かったというのはもっと驚きである。旅はつごう3度、試みられている。過去、ツアンポー峡谷に向かった5人の探検家と、カヌーでこの凶暴な流れを下ろうとして命を落とした日本人のエピソードを織り込み、物語は巧みに展開される。
旅はもちろんのこと「死」と隣り合わせである。覗いた「死の淵」は、高山の美しい風景の中でのそれではない。ジャングルの中の腐った木の根に足をとられ、谷へと滑落する。不快な蒸し暑さの中で際限なくダニに襲われる。
――人跡未踏の空白の五マイルに下り立ったとしても、私がやっていることといえば、延々と続く急斜面で苦行のようなヤブこぎをしているだけだった。(略)楽しいことなど何ひとつないのだ。シャクナゲの発するさわやかなはずの緑の香りが、これ以上ないほど不愉快だった。
だが、こう書いた直後に著者は「おい、おい」と独り言を漏らす。廊下状の岸壁に、巨大な洞穴がぽっかりと穴をあけ「異次元空間のような非現実的な雰囲気を漂わせて」いるのだ。あれはチベット仏教の理想郷「ベユル・ペマコ」じゃないか―。しかし、洞窟は対岸にある。入るには峡谷を大回りしなければならない。もちろん、橋など架かっているわけもなく、流れは歩いて渡れるほどやわではないからだ。著者はその旅を実行する。岩棚をたどってコンサートホールほどもある洞窟に着く。そしてそれは「空白の5マイル」のほぼ全域を踏破したことを意味する。
だが1か所だけ、心にわだかまりを残す場所がある。「門」と呼ばれる、切り立った崖が並立する峡谷の最も狭い部分。あの上になにがあるか、見てみたい。その動機が、5年の新聞記者生活を経た著者を動かす。それが3度目の旅である。
1000㍍の岩壁を越え、20日間を歩きとおして着いた村は廃村だった。引き返すだけの体力も食糧もない。その先の村にはたしかに人が住む気配がある。だが…。そこへたどり着くためには、ツアンポー川を越えなければならない。死の恐怖がむくむくと起きあがる。
――濃い緑とよどんだ空気が支配する、あの不快極まりない峡谷のはたして何が、自分自身も含めた多くの探検家を惹きつけたのか。
――極論をいえば、死ぬような思いをしなかった冒険は面白くないし、死ぬかもしれないと思わない冒険に意味はない。
著者は死の恐怖に立ち向かったわが身を客体化して見ている。これは凡人にできることではない。美しい風景のためでなく、さわやかな風のためでなく、ひとはなぜ未踏の地を目指すか。自分自身を透過してその答えを見つけようとするこの作業は、ツアンポー峡谷の踏破にもまして驚嘆に値する。そしてその作業は「凍」のように二つの才能によってではなく、たった一つの才能でなされている。
「空白の5マイル チベット、世界最大のツアンポー川に挑む」は集英社刊。1680円(税込)。初版第1刷は2010年11月22日。著者の角幡唯介は1976年、北海道生まれ。早大探検部OB。2002~03年、ツアンポー川峡谷の未踏査部を単独で探検。03年朝日新聞社入社、08年退社。09年、3度目のツアンポー川踏査。2010年、この作品で第8回開高健ノンフィクション賞。
山の図書館~「単独行者 新・加藤文太郎伝」谷甲州著 [山の図書館・映画館]
山の図書館~「単独行者 新・加藤文太郎伝」谷甲州著 |
「孤高の人」(新田次郎著)は長い間、私の愛読書であった。常人ではない足跡にあこがれたのである。加藤文太郎のように歩きたい。そう思っていた。いつしか、私の山を歩くスタイルも「単独行」になっていった。しかし、加藤文太郎のような「超人」にはなれなかった。
「その不死身の彼は実際は不死身ではなかったのですね」
「いや、不死身であった。彼は山で死ぬような男ではなかった。彼は極めて用心深く、合理的な行動をする男であった。いかなる場合でも、脱出路を計算したうえで山に入っていた」
槍ヶ岳の北鎌尾根で命を絶った加藤文太郎について、「孤高の人」文頭に置かれた問答である。しかし本当に「不死身」で「合理的」な男だったのだろうか。加藤は吹雪の中でも合羽をまとい、雪中ビバークをしたのだという。
(途中で天候が悪化したらどうする)
第一の加藤がいった。
「雪洞を掘ってビバークするさ」
第二の加藤が答える。
(寒いぞ、ものすごく寒いぞ)
「寒いことには馴れている。食糧はある」
(だが吹雪が、二日も三日も続いたらどうする)
「天候回復まで待つさ」
(「孤高の人」から)
加藤自身が書いた「単独行」を読んでみる。兵庫・氷ノ山での出来事である。
しかしスキーは下手だし、半分眠っているような状態でどうして満足な滑降ができよう。ちょっと辷ってすぐ自分から身体を投げ出すようだった。あまり苦しいので、歩いて下ったほうが楽に違いないと思って、スキーをぬぎ、それを一つずつ谷へ向かって辷りおろした。(略)そして僕は、もう駄目だ、ついに自分にも終わりがきたのだとこう思い出した。そして死ぬということが非常に恐ろしくなり、悲しみの声をあげて泣いた。そして、谷が「単独行者」でも取り上げている、加藤自身が記述した八ヶ岳での心象。
なぜ僕は、ただ一人で呼吸が蒲団に凍るような寒さを忍び、凍った蒲鉾ばかりを食って、歌も唱う気もしないほどの淋しい生活を、自ら求めるのだろう。――
一人の人間をめぐって、新田が描いたデッサンと加藤自身が描いたそれとは大きなギャップがある。新田は明らかに、加藤が記した心象風景をそぎ落としているように見える。もちろん「孤高の人」はフィクションであるから、新田が基本的な作法を誤ったわけではないし、新田が描く加藤文太郎はそれなりに魅力的でもある。
ただ、私のように「人間みんなちょぼちょぼ」と思っているものからすると、等身大の加藤文太郎も見てみたい気がするのだ。
谷の「単独行者」の末尾には主要参考文献が載っている。しかしここには「孤高の人」はない。このこと一つとってみても、谷がどのようなスタンスで加藤文太郎を描こうとしたかが分かる。
「第三話 はじめての冬山」。ここには氷ノ山でスキーを持て余したこと、八ヶ岳で年を越しながら凍った蒲鉾を食ったことなどの心象が入念に書き込まれている。「第四話 一月の思い出」は正月の剱岳を目指す話である。ここでは、5人のパーティーと麓の小屋で顔を合わせる。同行をしたいが、うまく言えない。付かず離れず行動するうち、パーティーからはうとんじられる。彼らが歩いた後をたどれば「ラッセル泥棒」と言われかねない。「失敬な奴だな。こんなところまで、追いかけてきて――」
あとの言葉はききとれなかった。それでも加藤に対する敵意だけは、明瞭に伝わってくる。(略)ラッセルのことなど口に出せる雰囲気ではなかった。
みずから望んだ単独行なのに、なぜそれに徹することができないのか。(略)自分の弱さが不甲斐なくて、腹立たしかった。(略)気がつくと、視野が涙でにじんでいた。正面から吹き付ける風のせいで、流れ落ちる間もなく涙が凍りついた。
加藤文太郎は不世出の登山家であることは間違いない。その彼をここまで弱い男として描くのはどうだろうか、という思いもしないではない。しかし、強さは時に折れてしまうが弱さはしたたかである。谷が描きたかったのはそういうことだろうと思う。そして加藤は単独行を自らの登山スタイルとしたが、厳冬期の北鎌尾根だけはパートナーを連れて登った。それが、最期の登山となった。
だから、怖かった。「人数が増えれば危険は増大する。もっとも安全なのは単独行」という原則は、やはり生きていたのかもしれない。かといって、単独行に戻るのは安易すぎた。意欲的な登攀を実践するには、単独行という枠組みは窮屈になっていた。(「第九話 北鎌尾根」)
初めて「単独行」でない登山を実践し、それが加藤の思考を狂わせた、という「孤高の人」の想定はおそらく正しいと思われる。しかし、それは「単独行」を貫けばよかった、ということには結びつかないだろう。もっと複雑な思いが加藤にはあったように思う。谷が描こうとしたのも、最終的にはそこだと思う。
「単独行者 新・加藤文太郎伝」は山と渓谷社刊、2500円(税別)。初版第1刷は2010年9月30日。著者の谷甲州は1951年、兵庫県伊丹市生まれ。1981年、カンチェンジュンガ学術登山隊参加。1996年、加藤文太郎をモデルにした「白き嶺の男」で第15回新田次郎文学賞。山岳小説では「遥かなり神々の座」「遠き雪嶺」などがある。
あらためて低体温症の恐怖を知る~山の図書館 [山の図書館・映画館]
あらためて低体温症の恐怖を知る~山の図書館 |
北海道・大雪山系トムラウシ山でツアー登山客18人のうち8人が亡くなったのは2009年7月16日だった。真冬ではない標高2000㍍級の山でなぜこんなことが起きるのか。ニュースの聞いた時の第一印象だった。そして当時のマスコミ報道は、登山客の装備の不備を取り上げた。観光客並みのウインドブレーカーで雨交じりの強風の中を長時間歩いたらしい。レインウエアはビニール製のものもあったらしい。本当だろうか。そんな装備で、3日間で40㌔余りも歩く縦走に出かけるだろうか。もし最新のレインウエアを着ていたら、遭難は起きなかったのか。
その後、この報道は間違いであったことが明らかになる。遭難者は全員、ゴアテックスのウエアを着ていたのである。マスコミの一過性の報道だけでは再発は防げない。事故の残したもう一つの教訓は、こうしたことでもあった。1年を経てこの書が出たことの意味はそこにある。大量遭難を招いた本当の原因は何だったのか。きちんとした検証が必要なのだ。
そうした観点から、4人のライターが分析を試みた。そのうちの一人、「山の遭難 あなたの山登りは大丈夫か」を書いた羽根田治が全体をまとめる形をとった。4人はそれぞれに別個のテーマでアプローチしているが、全体を通して見れば二つの大きな柱があることが分かる。一つは羽根田自身の問題意識によるところが大きい、「ツアー登山」が抱える問題である。もう一つは、知られているようで知られていない「低体温症」の恐怖である。
構成面からいえば、第1章として羽根田が事故当時のもようをできるだけ忠実に再現したドキュメントを掲載した。続いて第2章は、3人のうちただ一人生き残ったガイドへのインタビュー。第3章には事故当時の気象分析。そして第4章が「低体温症」で第5章に運動生理学面からの「提言」を載せた。第6章は再び羽根田で「ツアー登山」。ここでは、山で発生するリスクはツアー会社と登山客、いずれが負うべきかが論じられている。
このうち最も重要なのは第4章「低体温症」だろう。かつて「疲労凍死」と呼ばれたが、けっして酷寒の冬山でのみ起きるわけではない。事故当時の気象は第3章で触れられているが、特別な悪条件であったわけではない。風速はだいたい20㍍前後、台風並みだがありえない状況ではない。温度は8度から10度で夏としては寒冷だが真冬並みではない。雨量は午前6時の8㍉が最高で土砂降りではない。
しかし、稜線で強風にさらされ続け、沼からあふれた水で川状となった登山道を歩き続けるうち、体力が消耗していく。怖いのは、体温が下がっていくことへの自覚がないまま急速に意識が薄れることである。この書によれば、体温35度以下で歩行や意識に支障が出始める。正常な体温より、わずか1.5度の低下である。34度を下回れば、山では「死にいたる」という。これらの症状は段階的に発生するわけではない。普通、寒ければ震えがくるが、それさえないケースがある。第4章を書いた金田正樹は、トムラウシと同じ7月16日、大雪山系・美瑛岳で起きた遭難事故について、こう記している。
「十九時前、背負われて小屋に行く途中に、背中の上ですっとのけぞる形で意識がなくなった。小屋で蘇生術を行ったが、生き返ることはなかった。時間は二十一時だった」
疲労の度合によって低体温症の発生の仕方は違ってくる。体力を消耗しきってしまうと、体の震えによって体温を上げようとする防衛措置さえ取れなくなってしまうのだ。この点を金田は「低体温症の最も恐ろしい点は、意識レベルが下がるので自分の意志で防衛する動作さえできなくなることにある」という。
第1章のドキュメントを読んで分かるのは、昨今の中高年登山ブームもあって、装備に不備は見当たらない点である。この山行に合わせてゴアテックスのレインウエアを新調した人もいるほどだ。しかし、その装備を十分に使いこなしていたかどうかは疑問が残る。一方で、この縦走では宿泊する小屋は無人のためシュラフ、食糧は自分持ちである。当然、重量がかさむ。となれば持ち物を削るか、重量に耐えるか。削れないとすれば、果たしてそれだけの重量を担ぐ体力が備わっていたか。そして最大の問題点は、ガイドの経験不足である。山全般についてはそこそこのキャリアがあったかもしれない。しかしツアーに同行したガイドは現地で初めて顔を合わせた間柄。しかもコースを歩いたことがあるのは一人しかいなかったという。こうした事実から浮上する問題点を、羽根田が第6章で掘り下げた。
第2章にはただ一人生き残ったガイドへのインタビューを載せた。あの事故から1年を経たとはいえ、ガイド自身からすれば心から血を流すような思いのインタビューであろう。事実、このように語っている。
「この一年は長かったですよ。人生の中でいちばん長かったかもしれないですね」
そして、なぜ縦走路から引き返すことをしなかったか、について。
「『ヤバいよ。これ、マズイっすよ』と言いました。『やっぱり引き返そう』と言われるのを、どれだけ待っていたか。でも、『おまえ、なに言っとんだ』みたいな感じでそのまま先に行っちゃんたんで、『行くんだ…』と」
にわか仕立てのガイド集団の弱みが如実に表れている。だから第6章で羽根田は「事故の要因は『ガイドの判断ミス』の一点に尽きよう」と断言する。具体的には2日目の宿泊地、ヒサゴ沼避難小屋を出発してしまったこと、ロックガーデンの急登の手前で引き返さなかったこと、さらに北沼渡渉点を渡ってしまったこと、である。その背後にはツアー会社の、山のリスクに対する無理解、ガイド資格のあいまいさ、といった問題が横たわる。冒頭に書いたように、羽根田は「ツアー登山」のありかたに相当の問題意識を持っている。基本的に山では、リスク管理は自己責任だが、対価を払って参加するツアー登山はその範ちゅうに入らないともいう。しかし、トムラウシの例を見ると、あまりにも「誰かが何とかしてくれるだろう」といった意識が強すぎるようにも思える。だから羽根田は、自力で生還したある登山者の言葉を引く。
「結局、自分のことは自分で守るしかない。それがこの事故から得た教訓だ」
古今東西、万古不易の真理ともいえる。この言葉を心しなければならない。
「トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか 低体温症と事故の教訓」は山と渓谷社刊。初版第1刷は2010年8月5日。1600円(税別)。羽根田治はフリーライター。金田正樹は整形外科医でヒマラヤ登山の経験もある。このほかの著者は日本山岳会、日本雪氷学会会員の飯田肇、チョ・オユー無酸素登頂を果たし登山の運動生理学を研究する山本正嘉。
山に人間の深淵を見る~山の図書館 [山の図書館・映画館]
山に人間の深淵を見る~山の図書館
「山で見た夢 ある山岳雑誌編集者の記憶」(勝峰富雄著)
いきなり「さよなら山登り」で始まる。山登りの記録を期待していた読者は途方に暮れるだろう。そうなのだ。これは一点から一点へ、どのようにリスクを回避しどのように素早く行動したか、という記録集ではない。若い日には尖鋭な登山にもあこがれた著者は、どちらかといえば自らを「沢ヤ」だという。道さえも定かでない山の深奥部に分け入る。沢から沢へ。山と一体になる、そんな感じを求めている。だから著者は「登山」や「山登り」という言葉は、人間と山の関係の一面しか表現していない、という。そこからもっと、山と人間のいまだ名づけようもない広範な関係を求めていく。これがこの書を書くことになった「動機」だという。
そして第一部。「山頂の記憶」「山波の記憶」「雪陵の記憶」などと「記憶」シリーズを展開する。これまでの「登山」での印象的なシーンを書き連ねているのである。しかし、それは行動の記録、もしくは記憶ではない。山が自らの存在と人生にどのような影を落としてきたかを語る。山を書くことで著者自身の「深淵」が見えてくる仕掛けになっている。
あのとき命を繋いだザイルは、今もどこからか自分へと延びている。(略)だがその質量のないザイルは、臍の緒のように、生きている「根拠」を与えつづけてくれている。(「岩陵の記憶」)
じっと氷を見つめていると、青い氷の底からなにかが浮かび上がってくる。女の顔だった。(「蒼氷の記憶」)
第二部「山嶺を越えて」は比較的、山の行動の記録として読むことができる。その範囲は、北アルプスなどメジャーな地域にとどまらない。むしろ知られざる山域をこそ、著者は目指しているかのようだ。
秋山郷。(「山里のマグリット」)
そして伯耆大山、出羽三山、秋田・森吉山。
第三部は「渓、そして秘境へ」。沢をめぐり、幻の池にたどりつく。濃い霧が「ハヤクカエレ」と言っているようだ―。九州では「奇跡の谷」を遡行する。すでに文体は幻想の色を濃くしている。「谷の朝はいつも一瞬にして始まる」と書く「九州幻流行」。
曖昧だった自分のなかの地図が少しだけ明確になった。と同時に、それがごく一部であることをあらためて思う。なぜなら、山顛の向こうに刻まれた、幻のように霞む無数の谷を見てしまったから。
このとき著者は、登るべき山や渓を見ているのではない。自分が寄り添うべき自然の懐の深さを思っているのである。副題にもあるとおり、筆者は山岳雑誌の編集者を13年間務めた。山行を記録することから始めたに違いないが、それはいつしか思索の記録としての色彩を強めていく。沢を詰め、山の深淵に迫る姿はそのまま人間の存在の深淵に迫る姿と重なる。ノンフィクションとしてより、むしろフィクションとして読むほうが著者の息遣い、鼓動が分かるだろう。
「山で見た夢 ある山岳編集者の記憶」はみすず書房刊。2600円(税別)。初版第1刷は2010年5月15日。
著者の勝峰富雄は1965年生まれ。高校ワンゲル部で山登りをはじめ早大稲陵山岳会に入り尖鋭的な登山に目覚める。卒業後は沢登りに傾倒。学習参考書の編集に携わる。30歳で山と渓谷社に転職。「山と渓谷」編集長を経て出版部プロデューサー。
山の図書館~みずみずしい抒情の記録 [山の図書館・映画館]
山の図書館~みずみずしい抒情の記録
山口燿久「北八ッ彷徨」
昭和の初めに生まれ、10代のころに登山を始めたという。昭和19年に獨標登高会を創立、初代代表となる。
と書けば、戦火の時代に山を切り開く、ごつい山男のイメージがわきあがる。しかし、この「北八ッ彷徨」に収められた写真はそれらを見事に裏切る。眼鏡をかけ、皮の登山靴をはいてどこかの斜面で休息する男性は、どう見ても内向的な優男である。
そしてこの書の文章もまた、このイメージから外れることはない。
――ぼくが山に登りはじめて、もう何年になるだろう。苦しかった山があり、こわかった山があり、さびしかった山があった。苦しい山や、こわい山にはめったに追い返されはしなかったけれど、さびしい山にはときどき敗けた。敗けて帰ったじぶんの弱さは、いつまでも肚にこたえた。(「岩小舎の記」)
うん。分かるな、この感じ。
八ヶ岳を歩いたことのある人なら誰でも知っているが、北八ッと南八ッはまったく性格が違う。著者も当然、この点に触れている。
――南八ヶ岳があけっぴろげで明るく、派手な山であるのにくらべて、北八ヶ岳は内にひそんで暗く、地味な山である。(略)切り立った線はそのてっぺんに登ってやろうという人間の本能を挑発するが、なだらかな面はそういう情熱を刺激しない。(略)要するに登山という構えた言葉よりも、山歩きとか山旅とかいうおとなしい言葉のほうが、このおだやかな山地には、すなおにひびく。
著者は明らかに、北八ヶ岳に魅力を見出している。頂上を必ずしも必要としない山歩き。原生林に、著者の思索と抒情に満ちた感性があふれ出ていく様子が見える。だからこの書も「八ヶ岳彷徨」ではなく「北八ッ彷徨」となったのであろう。
著者の豊かな抒情的感性は、多くの作家がそうであるように「死」のイメージで縁どられている。そう思わせる表現が、そこかしこにある。そのルーツとも思えるもの―。この書の末尾には「富士見高原の思い出」というわりあい長めの文章が収められている。著者が結核を患い、八ヶ岳のすそ野で長い療養生活を強いられたときの経験を書いている。
――ふと、いま自分が寝ているこの同じベッドで幾人かの人が死んだはずだということに気づいた。(略)自分はいま少なくとも幸福とはいえないが、死につつある隣室の人よりかは不幸ではないと思った。
――小広い平地になってひらけたその峠は、風と雪と、乱れ飛ぶ落葉樹の落ち葉の、すさまじい狂乱の舞台だった。(略)
滅びるものは滅びなければならぬ。一切の執着を絶て!(「落葉松峠」)
この無常観。そしてこの文章は、こう締めくくられている。
――心を澄ませば、なにもかも美しすぎる山の春の自然だった。
そうした中で、「岩小舎の記」の章は一味違っている。「岩小舎」があるのは北八ッではなく、南の八ヶ岳の稜線。阿弥陀岳の頂上下、ほとんど人の入ることのない沢にそれはある。地元の人も、存在は知ってはいても場所を知らない「岩小舎」の入り口を偶然見つけ、以来、壁を登る際の拠点としてきた思い出をつづっている。北八ッを歩く時の思索に満ちた文章とはがらりと変わって、ここには著者の山男としての「強さ」と行動力がにじむ。
いずれにしても、雨の日に山を歩けない無聊を紛らわすため、「北八ッ」をさまよってみるのに最適の著と言える。そしてこれを読めば、間違いなく八ヶ岳の自然をめぐりたくなる。
著者は1926年、東京生まれ。後立山不帰Ⅱ峰東壁などルート開拓。串田孫一らと山の文芸誌「アルプ」編集に参加。主な著書に「八ヶ岳挽歌」(平凡社)など。
山の図書館~「エベレストの神話」に挑む [山の図書館・映画館]
山の図書館~「エベレストの神話」に挑む
「マロリーは二度死んだ」(ラインホルト・メスナー著)
ジョージ・マロリー。1886年、イギリスで生まれる。ラインホルト・メスナー。1944年、イタリアで生まれる。共通項は登山家。マロリーは1924年、3度目のエベレスト挑戦で消息不明となり、「登頂」をめぐって論争を巻き起こす。75年後に遺体がほぼ完全な形で見つかったが、論争は決着していない。メスナーはエベレストを無酸素単独登頂。「ヒマラヤより高い山に登ることは不可能だし単独行より少人数の遠征などありはしない」【注】と語って山を降りる。マロリーは多くの謎を残したことでエベレストの神話となり、メスナーはすべてをやり遂げたことで神話とはならなかった。
2人の、おそらく不世出の登山家が「エベレスト登頂」の謎をめぐって語り合う。メスナーが、ある時はマロリーの目となり、ある時は天空を飛ぶ鳥の目となり…。それは1999年のマロリーの遺体発見時のもようから始まる。こんな風な語り口だ。
「もう何週間も前から私を探していたという者たちが、私がひっそりと憩っているこの場所に突然やってきた」
マロリー=アーヴィン調査遠征隊の隊員が目にした、標高8250㍍のテラスの上に横たわる「白くて細長い奇妙な物体」-。それが、マロリーのほぼ完全な遺体だった。うつぶせで、鋲靴をしっかりとはいていた。背中はむきだしで白い大理石のようだったという。
一転、舞台は1924年へと移る。頂稜を行くマロリーとアーヴィンを目撃したのは、地質学者でもあったオデルである。
「頂上がはっきり見えた。頂上ピラミッド手前の、上から二つ目の段差の下に、黒点を一つ見つけた。それは岩の段差に近づいていった」
マロリーが挑んだ稜線はヒラリー・ルート(南東稜)とは反対側の北稜だった。ここには岩の難所がある。いわゆる第2ステップで、この垂直の壁を登るか、それとも北壁を巻くか。どちらも困難であることに変わりはない。オデルが見たのは第2ステップの下部だったのか、それとも上部だったのか。第1ステップの近くだったのか。第2ステップに取りつくところを見たと証言するが、疑問視する声は多い。そしてここが議論の分かれ目になっている。第2ステップを越えれば頂上まで約250㍍、ほぼ平坦な稜線が続くだけだからである。もしマロリーが登頂を果たし、下山中の姿をオデルが見たのだとすれば…。
1933年には別の遠征隊によってピッケルが見つかる。第1ステップの手前、マロリーの持ち物と分かる。だが、謎を解く鍵にはならない。謎は深まるばかりだった。その後も遠征隊が続々とエベレストに乗り込む。1953年、ヒラリーとテンジンが、南面からの登頂に成功する。中国は1960年に大規模な遠征隊を送り込み、マロリー・ルートから登頂したと発表するが、メスナーは疑問を呈する。第2ステップを人間ばしごで乗り越えた? 本当だろうか。登頂は深夜だったというが、これも本当だろうか…。だがその一方で、だれもマロリーの遺体に気づかない。
焦点は、マロリーが第2ステップを越えたかどうかだ。メスナーはオデルにも直接会い、確かめる。そしてメスナーとしての結論を出す。とてもそこまで書くわけにはいかないだろう。ぜひ自分の目で確かめてほしい。
それにしても、神は一人の人物に二物も三物も与えるものだ。細かい事実関係で疑問点はあるというものの(訳者自身が、あとがきでそう書いている)、一流の登山家による縦横無尽の筆さばきには感心する。意味深なタイトルの意味も、読めば分かる。
ところで「2度死んだ」マロリーは、これで永遠の眠りについたのだろうか。いや、マロリーはきっと今もエベレストの風になって山稜を漂っているに違いない。神話は終わってはいないのだ、と思う。
【注】「ラインホルト・メスナー自伝 自由なる魂を求めて」から。
山の図書館~45億年のロマン [山の図書館・映画館]
山の図書館~45億年のロマン |
「日本の山と高山植物」(小泉武栄著) |
山に登ると、周りの景色を眺めては「ああ、いいなあ」と思い、路傍の花に見とれては心を癒される。下山すれば明日への活力がみなぎる自分がいる。そんなとき「ちょっと待てよ」とは思わない。この山はどういういきさつでできたのだろう、とか、あの山とこの山はどうして形が違うのか、とか、この花はどこから来たのだろう、とか。普通考えないものである。それを考えてみる。思いをはせてみる。もし、そういう気持ちがあるなら、この本はあなたにとって最適の友になるに違いない。
「日本の山はなぜこんなに美しいのだろうか」。著者はこう書き出す。海外の山を知らないので日本の山が相対的にどのような価値を持つか考えてみたこともないが、著者によれば日本の山岳は氷河こそ持たないものの、それ以外のあらゆるものがそろっているという。この多様性こそが特徴だという。例えば槍穂や剣なら岩壁、ナイフリッジ、カール、モレーン。白馬なら大雪渓に多彩なお花畑。凡人である私たちの感性はしかし、これらの風景を見て感嘆するにとどまる。著者はその先を探索する。たとえば気象条件。世界に例を見ない強風と多雪。ジェット気流が日本海で合流し、冬の強風を生む。そこに対馬海流から上昇する暖気がぶつかる。日本の山の厳しさと美しさが生まれる。北アルプスに行けば夏でも残雪のある風景と出会うが、これも世界的に見れば珍しいのだそうだ。
高山植物の多くは北方系だとされるが、それはどのように南下したのだろうか。千島やサハリン、ユーラシアの北方から、氷期に海を渡ってきたらしい。その伝播には火山活動も貢献しているという。森林が破壊され、その後に北方から渡ってきた植物が芽を出す。
「ヨーロッパアルプスにはなぜハイマツ帯がないのか」「日本の山はなぜ森林限界が低いか」「日本の国土は地層の博物館のように複雑だ」―。著者は、世界的に見て日本の高山は「正統派」であり、複雑で繊細な美しさを持つという。これらを主に地質学の観点から詳細に解き明かし、プレートテクトニクス理論を用いて山脈の形成にまで踏み込むが、ここでそれらを一言にまとめるのは難しい。直接読んで自然の不可思議さを味わっていただきたい。
地球は約45億年前に誕生したとされるが、現在の地形が形成されるにいたった最終氷期からは1万年である。既に縄文時代は始まっていた。1万年は人間の持つ時間で考えると長いが、地球史の中では1冊の書物の最初の1文字にすぎない。私たちはそのまた一瞬の時間の中で山に登り、感嘆し、癒されているわけだ。ときにはそんなロマンに浸るのもいい。
地質や気象や植生やその他の分野について、それぞれ専門的に掘り下げた書はあるが、これほど各分野を総合的に考察した仕事を、ほかにしらない。分かりやすく書いてはあるが、学術的な部分もあって読むのに忍耐を要するところもある。そんな懸念がある場合は同じ著者の「山の自然学」がお勧めだ。「氷河時代の植物群 礼文島」や「森林限界がなぜ低いか 早池峰山」「二重になった山稜 雪倉岳」のように、山ごとにトピックをまとめてある。訪れた山のイメージを描きながら読むと分かりやすい。「日本の山と高山植物」が総論であり「山の自然学」が各論-と言えるかもしれない。
「日本の山と高山植物」は平凡社新書。初版第1刷は2009年9月15日。
「山の自然学」は岩波新書。初版第1刷は1998年1月20日。
小泉武栄氏は1948年長野県生まれ。東京学芸大教授。専門は自然地理学。山の図書館~「疲労凍死/天幕の話」(平山三男著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「疲労凍死/天幕の話」(平山三男著)
昨年の夏、北海道のトムラウシ山でツアー中の9人が亡くなった。緯度の高い北海道とはいえ、7月のことである。亡くなった中には経験豊かなガイドもいた。「なぜ」という疑問符は、いまだに心を去らない。この時、遭難した人たちの直接的な死因は低体温症、つまり「疲労凍死」だった。
時に遠征したりすると、無理をすることがある。「いっぱいいっぱい」なのに歩いてしまう。幸い大事に至ったことはないが、山小屋に入ってなぜか寒く、布団をかぶってもガタガタ震えることがある。体温調節機能が壊れている。「ああ、バテてるな」と自覚する。
この「疲労凍死」で取り上げたのは55年前の事故である。2000㍍に満たない那須連山。残雪があるとはいえ、5月の出来事だ。歩きなれた地元の山。2泊3日の行程。そんな中でなぜ高校山岳部の、引率教師を含めた16人中6人が亡くなったか。著者は彼らの行動を詳細に追いながら、だれもが遭遇するかもしれない惨事を再現する。
二つ玉の低気圧。気温3度。風速10㍍以上の風。長い稜線…。そう、これはあの「トムラウシ」に酷似しているのだ。そのうえで、当時は携帯ラジオが普及していなかったこと、雨具が現在のようなゴアテックス製などおよびのつかないものであったこと…などの悪条件が重なる。
「疲労凍死/天幕の話」の表紙 |
丹念に裏付けられた事実が、抑えた筆致で描かれる。救助されたものと、されなかったもの。残酷なまでの対比。そんな中で、部長を務める3年生の母の、ただ山を見つめるたたずまいが共感を呼ぶ。母一人子一人なのだ。感情を抑えきったかに見えた母はしかし、引率教諭の自宅に出向き、叫ぶ。「私の息子を返せ」と。「あとがき」によると母の行動は事実に基づくという。
著者の平山はある女子高の山岳部を率いてヒマラヤ登頂を成功させた経験を持つ。それだけにこの母の叫びは重いのだ。どんなことがあっても、山で死んではならないのだ。
「天幕の話」は、死んでしまった山男との、永遠ともいえる対話である。単独行の天幕に、ウイスキーの入ったカップが二つ。語られるのは目の前にある「死」の手触り、におい、光景である。それらが幻想的な筋立てで展開する。「『天幕の話』外伝」として編まれた「桃井の恋」とともに「山男なら分かる」味わいだ。
ここにあるのは小説家による山岳小説ではなく、まぎれもなく登山者による小説だといえる。一つ不満なのは、タイトルが即物的なこと。でもこれも、山男の武骨さと思えばいい。
「疲労凍死/天幕の話」は山と渓谷社刊。1700円(税別)。初版第1刷は2009年10月1日。「疲労凍死」は「山と渓谷」に「天幕の話」「『天幕の話』外伝 桃井の恋」は「山の本」に連載、もしくは掲載。
平山三男は1947年、栃木県生まれ。立川女子高教諭として同高山岳部のヒマラヤ・ゴーキョ遠征に同行。この時の体験をまとめ出版したことがある。現在は東洋大文学部講師。山の図書館~「山の遭難 あなたの山登りは大丈夫か」(羽根田治著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「山の遭難 あなたの山登りは大丈夫か」 |
中高年の登山ブームが取り上げられて久しい。さまざまなケースが考えられるが、ある年齢に達して、時間が有効に使えしかも健康にもいい「山歩き」を始める人は結構多いのだろう。だがそういう人たちは組織的な訓練を受けていないケースがほとんどだ(偉そうに書いているが、私の場合もそうだ)。そんなとき、集団での登山を選ぶか、単独行を選ぶか。近年の実態をみると、単独行の「敷居の低さ」は大きな魅力でもあるのだ。そしてこの「単独行」というスタイル、なんとなく日本人の心情に合ってもいる。
私も、実は単独行が多い。一人でなら山と直接向き合い対話ができるからだ。好きなペースで好きな時間だけ山を眺め、好きなポジションで写真を撮れる。集団であれば、まず他のメンバーと向き合わねばならない。その一方、単独行では遭難するリスクが当然大きくなる。例えば昨年、白馬尻の小屋で聞いた話。雪渓で行方不明になるケースは圧倒的に単独行が多いという。クレバスにはまればそれっきり。複数だと救助を求めることができる。わが身に照らせば、こんなこともあった。沢沿いの山道を下っていて、つい道を見失ってしまった。途中で道は沢を外れているのだが、そのまま下ってしまったのだ。幸い途中で気づいて引き返したが、もしもそのままどんどん下ってしまっていたら…。進退きわまる最悪のケースも想定される。でも単独行はやめられない。
「山の遭難 あなたの山登りは大丈夫か」(平凡社新書、税別760円。初版第1刷は2010年1月15日) |
登山の危険を説く本は多い。だがその多くは教訓的な事例を並べ、著者の経験に頼った結論を導き出す。こういう本は読んでもあまり参考にならない。しかしこの「山の遭難」は少し違っている。一貫して実証的な姿勢で書かれているのだ。例えば「中高年の遭難事故が増えたワケは?」の章。確かに最近の遭難者をみると8割は中高年だ。しかしこれは中高年の登山者が増えている(分母が大きくなっている)ためであり、「中高年は遭難のリスクが大きい」という結論にそのまま結び付かない。このことを、警察庁集計のデータに基づいて説明する。
井上靖がナイロンザイル事件をもとに「氷壁」を書いたころ、登山とは例えば厳冬期の北アルプスの壁を登ることだった。魅力的な壁を持つ谷川岳では毎年、記録的な死者を出した。だが昨今の登山ブームは違う。「その敷居の低さによるところが大きい」のだ。だがここで誤解が生じる。いくら時間とカネをかけても、潜んでいる危険はなくならない。
このあとの細かい分析はこの本に任せよう。著者は「単独行」そのものを否定しているわけではない(なぜなら自身も単独行を好んでいるらしいから)。ただ、そのリスクを一人で管理できるか、万一に備えた対策をとっているかを問いかける。行先はだれかに告げておかなければ話にならない(私自身もこれは徹底している)。そのうえでこう書く。「無用のトラブルを避けるために、山に行く前には救助要請をしてもらうタイムリミットをチャンと決めて、家族らに伝えておくようにしよう」。その通りなのだ。
後半は「遭難事故のリアリティ」としてさまざまな事故の概要をまとめた。助かった人と助からなかった人。分かれ目は何か。予期せぬ事態に陥って冷静でいられる人は少ない。だから常日頃から遭難のニュースを聞くたびに「自分ならどうする」とシミュレーションを重ねること。「こんなところで死んでたまるか」と生への執念を燃やすこと。それでもなお山は「運が生死を左右することが多分にある場所」なのだ。それを十分に頭に入れたうえで山に登ることなのだ。
最後の章「なぜ増える安易な救助要請」はタクシー代わりにヘリを使う人、命がけの救助隊に携帯で「早く来い」という登山者…。読めば読むほどおぞましい。大きな山行の前には保険に入っておくようにしているが、これも善し悪しなのだ。ときに「保険に入っているから費用はいくらかかってもいい」と、安易な要請につながる例があるからだ。 あとがきで「いざ書き始めると登山者に対する苦言ばかり」と書いているように、こうした本はそういう傾向になりがちだ。でもこの本が抵抗なく読めるのは、冷静な分析と実証的な姿勢を保ち続けているからだろう。わが身に照らし合わせながら、ぜひ読んでいただきたい。
【注①】日経新聞12月30日付社会面
【注②】著者は1961年生まれのフリーライター。著書に、極限状況を生き抜いた登山者のドキュメント「生還」など。
山の図書館~地上に降りた物語の天使~笹本稜平「未踏峰」 [山の図書館・映画館]
地上に降りた物語の天使~笹本稜平「未踏峰」 |
前2作とは違って「未踏峰」は架空の山を舞台にした。国家間の空中戦ともいうべきプロットで組み立てた「天空-」、会社経営者をヒマラヤ8,000㍍峰の頂上に立たせる、という「還るべき―」と比べると、今回ヒマラヤのサミットに挑む3人は社会のマイノリティーの色彩が強い。宇宙の高みから社会の上層、そして今回は障害を抱える若者たち。それが何によるものかは分からないが、著者の視線の位置は確実に降りてきている。
システムエンジニアからドロップアウトした橘裕也。知的障害を抱える勝田慎二。そして戸村サヤカはアスペルガー症候群に悩み続けた。小説の冒頭この3人が、息をのむヒマラヤの景観を目前にする。笹本の山岳描写はここでも健在だ。
| 笹本稜平「未踏峰」の表紙(祥伝社刊、1700円、初版第1刷は2009年11月5日) |
「急峻な西稜となだらかな南東稜の二つのスカイラインが中空の一点で交差する。その秀麗な山容は、天にはためくタルチョ(祈祷旗)のようだった。
急角度で稜線に駆け上る南壁は、神の匠の技とも思えるヒマラヤ襞に覆われて、削ぎ落とされたような氷壁の中間部には銀の胸飾りのような懸垂氷河」
なぜ、この3人がヒマラヤを目指すことになったのか。パウロさんと呼ばれる、ある山小屋の主人。いつもはにかむような表情で客を迎え入れる。目立たないが登山者にとってどこかホッとさせる存在。彼は世界の一線級のクライマーと呼ばれてもいい力量の持ち主だった。それが、ある体験を経て登山界を退き、山小屋にこもる。そして彼の見えない力とでもいっていいようなものが、3人を引き寄せる。
3人が出会った後、パウロさんは山小屋の火事で焼死してしまう。残された一通の遺書。「告白しよう。私は人を殺した―」。その言葉は「鋭利な鏃のように」裕也の心を貫く。懺悔のように、詳細な物語がつづられる。ダウラギリⅠ峰遠征。アルパインスタイルによる無酸素登頂が試みられる。パウロさんは有酸素と無酸素の同時登頂を提案する。そして自ら「無酸素」を選択する。先行する2人を追うパウロさん。「ふと横手の斜面に目をやると、ガスの切れ間に赤いものが見えた。(略)それは間違いなく人間だった」
そのとき、パウロさんは信じがたい行動を取る。「その隊員が着けていた酸素マスクを外した。隊員はかすかに顔を歪めたが、意識を取り戻す気配はなかった」
頂上を踏んだパウロさんは引き返すが、すでに隊員の体は氷のように冷えていた―。以来、慙愧の思いがパウロさんの心を蝕んでいく。
パウロさんの小屋で出会った3人は、かつての名クライマーの教えを受けて冬の南八ヶ岳、富士山を歩き、めきめき上達する。パウロさんの思わぬ死を目の前にして、その遺志を継ぐこと―残った3人でヒマラヤの未踏峰を登ること―が、自分たちの宿命であることを胸に刻む。
架空の未踏峰「ビンティ・チュリ」(祈りの峰)の頂上が見える標高5,000㍍のコルに着いたのは早朝だった。
「『あ、太陽が覗いた』
サヤカが唐突に声を上げる。彼女が指差す彼方の雲海上に融解した銑鉄の雫のような真紅の光点が現れて、矢羽根のような光芒を幾筋も伸ばしながら急速に明るさを増してゆく」
そんな光景を見ながら裕也はつぶやく。「まだ終わっちゃいない。おれたちをあの頂に立たせることがパウロさんの夢だった。おれたちにとっては、それに挑戦することが、人生を生き直すための希望の源だった」
そして3人は、これ以上高いところがない場所に到達する。
「私たち、でっかい希望をもらっちゃったね。パウロさんから」
「ああ。だからおれたちも、パウロさんの希望を引き継ごう。ビンティ・ヒュッテを再建しよう。おれたち三人で―」
頂上までの途中、苦しい中でサヤカがつぶやく。
「生きてるって不思議だね―」「本当の自分が生き生きと手足を伸ばしているの」
地上に住む普通の人間たちにとって、名もなき峰の頂が「希望の峰」になった瞬間を、笹本は鮮やかに描いている。
山の図書館~「ヒマラヤ世界」(向一陽著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「ヒマラヤ世界」(向一陽著) |
共同通信社で社会部長などをつとめた向一陽さんは、もう70代半ばになる。若いころは南米などにおもむき、数々の探検記をものにした。定年退職後の2001年、1冊の本を著した。「『ヒマラヤのトレッキングに行こうよ』。妻がそう言いだしてくれた。アンナプルナに憧れていたでしょ。定年記念に、アンナプルナを眺めるトレッキングに行こうよ」。こんな書き出しで始まる「トレッキングinヒマラヤ」は夫婦共著、カラー写真満載の楽しい本だった。
その向さんがもう一度、ヒマラヤに関する本を出した。だがこれは、楽しい本ではない。地球温暖化や人間がもたらした汚染にあえぐヒマラヤのルポである。8億の人々がかかわるというこの地域の未来に向さんが警鐘を鳴らす。
「ネパール・ヒマラヤ全域では、年間のトレッカー数は約10万人だ。ネパール中央部のリゾート地ポカラにあるACAP(アンナプルナ自然保護プロジェクト)の計算では、15人グループの10日間のトレッキングでは生ごみ15㌔が出る。ロッジは一日に薪300㌔を燃やしている」。しかしヒマラヤの自然の崩壊は、こうした人的破壊にとどまらない。深刻なのはノルウェー外相も指摘している氷河の衰退だ。
「ヒマラヤ世界」(中公新書) |
「ここ3年ぐらい、行くたびに氷河の上の池が広がっている。(略)今年はすごい流れになっていました」
実際「氷河湖決壊洪水」(GLOF)の懸念は高まっているのだという。1985年8月、ナムチェの足元の川で山津波発生。高さ60㍍の天然ダムが決壊し、人家や橋を破壊した。この湖は1965年の時点では影も形もない。20年間で湖ができ、消えた。著者によれば、2040年までにヒマラヤのほとんどの氷河は消えてしまう、という予測もある。氷河はモンスーンの豪雨を蓄える保水機能を持つ。この氷河がなくなったら…。ヒマラヤにぶつかる膨大な湿気はそのまま山腹を流れ下ることになる。雨期には大洪水、乾期には干ばつの恐怖が増大する。当然、農業をはじめとする多くの産業に大打撃を与える。
広島のある学校で教職についていた大木章次郎神父はいま、ポカラで子供たちの面倒を見ている。その大木さんの言葉。「カトマンズは機械が汚す。ポカラは人間が汚す。外国人が汚します」。そして「今は子供たちを湖で泳がせたくない。目を悪くする」。その湖、ベワ湖は著者によると「白い逆さヒマラヤを映しだして、息をのむ美し」さだという。
森林伐採も大きな問題だ。「山腹は伐採跡が天に至っている。(略)これではモンスーンの豪雨はどっと山を駆け下ってしまう。『ネパールが木を切るから洪水が起きる』。下流のバングラデシュの人たちの非難の声が聞こえるような気がする」。森が減れば動物のすみかも減る。再び大木神父の証言。
「最近、ヒョウが麓から上がってきて、犬を襲っています。麓の木がなくなっているのです。うちの犬も去年、やられました」
アフリカを起源とする人類は東へと移動し、ヒマラヤにぶつかって滞留。その後、南と北にわかれてさらに東を目指したのだという。10万年を単位とする人類史の俯瞰。そしてインドを含むこの地域の文明は5000年の歴史を持つ。2000年と言われる日本の文明など足元にも及ばない。その悠久の大地が危機にひんしている。
山岳とはあまり関係を持たないが、石弘之「キリマンジャロの雪が消えていく」も、おなじような問題意識で書かれている。キリマンジャロの山頂氷河は年平均50㌢ずつ後退し、このままのペースだと2020年までに消失するという。アフリカ環境問題を論じたこの本では、当然のことながら人口爆発、乱開発、貧困や内戦にまで言及している。「アフリカは世界史から消えつつある」(W・ポスト紙)に対して「アフリカを消し去ってはならない」との著者の思いが、この本を実現させた。向氏も石氏もともに元ジャーナリストという経歴を持つ。
「キリマンジャロの雪が消えていく」(岩波新書) |
【注②】「ヒマラヤ世界 五千年の文明と壊れゆく自然」は中公新書、880円(税別)。2009年10月25日初版。「キリマンジャロの雪が消えていく アフリカ環境報告」は岩波新書、780円(税別)。初版は2009年9月18日。
山の図書館~「雨過ぎて雲破れるところ」(佐々木幹郎著) [山の図書館・映画館]
「雨過ぎて雲破れるところ」(佐々木幹郎著) |
変な言い方だが、全編の基調は「まじめに遊ぶ」ことの追求である。そのことによる解放感。だから、例えば焚き火一つとっても、こんな風になる。
「風には『風の目』というものがある。必ずそれは燃え上がった焚き火の、木を組んだ隙間の一点だけにあるから、焚き火の炎の形と向きによって、風の目を見つけるのだ。その一点をめがけて、団扇でゆっくりとあおぐ。そこを外して、他の方向から団扇を使うと、いくら力強くあおいでも、かえって火は弱まってしまうのだ」
手に入れたカジカで骨酒をつくる。焼き具合にこだわり、天日に干す。
「一口飲んで、全員が感嘆の声をあげた。なんというふくよかな甘さなのだろう」
「雨過ぎて雲破れるところ」(みすず書房刊) |
中原中也研究で知られる著者とフォークシンガー小室等との交流では、中也の詩「サーカス」に小室が音をつける。「これまで聴いたことのない、やわらかな『サーカス』」で「一番いい!」と叫び「まるで二十年ほど前からの友人だったような感覚」に陥り、明け方まで飲んで騒ぐ。装丁の帯にある「詩人のコミューン」が出現する。
東京芸大の学生が山小屋を訪れてコンサートをしたときのこと。村の子供たちも参加する。翌日、子供たちが芝生で水を掛け合って遊んでいた。服が脱ぎ捨ててある。「少女たちは音楽とダンスですっかり身体を解放され、最後は裸になってしまったのである」
タイトルは中国の「雨過天晴雲破処」から。雨上がりの空の新鮮な青。青磁の理想の色を表す。アジアを放浪する視線の一端が分かる。
山の図書館~「ヒラリー自伝」(E・ヒラリー著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「ヒラリー自伝」(E・ヒラリー著) |
1975年、エヴェレストの初登頂者ヒラリー卿が来日。案内をしたのが吉沢だった。なぜヒラリーと面識があったのか。多くの著作の翻訳者でもあったからである。
この年「山と渓谷」に寄稿した吉沢の文章から。
「開けっ放しの性質が行間ににじみ出ている、ということである。つまりケチケチしたずるさがないということにもなろうか。彼はいわゆる芸術家でも学者でもない。早く言えばエヴェレストへたまたま一番乗りをした蜂蜜屋の兄ちゃんであった」(「自伝」から引用)
自伝にはヒラリーの写真が何枚か収められている。「ヴィクトリアで名誉法学博士号を授けられるヒラリー卿」は、吉沢が描くそのままの横顔だ。
「ヒラリー自伝」(草思社) |
しかし当然のことながら、ただの素朴な男ではない。登山に関しては精緻な記録を紡いでいく。
「四分の三入っていたボンベを使い切ったので、それを棄て、今度は軽い九㌔のボンベをつけた。(略)我々は1分間に3㍑ずつ吸った。(略)高度を上げないようにして、固く凍った雪にステップを切りはじめた」。「ついに私は、とびきり大きな瘤の背にステップを切り(略)ゆるい雪稜を登りきった。目標に到達したことがすぐに分かった。(略)エヴェレストの頂上に立ったのだ」
ヒラリーは自伝の後半で次のように書く。
「これまで私は新しい冒険を見つけるのに苦労したことは一度もなかった。いちばん苦労したのは、それを実行する時間を見つけることだった」
原題は「NOTHING VENTURE, NOTHING WIN」。「冒険のない人生なんて」とつぶやいているようだ。たまたまエヴェレストがそこにあったから、と言っているかのようなニュージーランド生まれの男の人生がある。
山の図書館~「栄光の叛逆者 小西正継の軌跡」(本田靖春著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「栄光の叛逆者 小西正継の軌跡」(本田靖春著) |
本田は01年、糖尿病で両足を失う。さらに大腸がん、肝がん、右目失明、心筋梗塞、脳梗塞とあらゆる業病をねじふせ、病室でペンをとる。しかし闘病のことなど触れることはない。さりげなく「私は闘病記と貧乏物語が大嫌いである」と書く。
「私は折りに触れて、自分のことを由緒正しい貧乏人といってきた」という本田の真骨頂ともいうべきエピソード。ある大学教授と取材のため京料理の店に行く。いかに粋を極めた料理かと講釈が始まる。店の親父も合いの手を入れる。「何を出ししましょう」「なるべく能書のつかないものをちょうだい」
「栄光の叛逆者」のあとがきで本田は「私は山に関してまったくの門外漢」と書く。その彼が生涯に2冊、登山に関する著作を残した。「K2に憑かれた男たち」と、この「栄光の―」である。その動機を本田はつづる。
| 「栄光の叛逆者 小西正継の軌跡」(山と渓谷社) |
「(ある雑誌の編集者が登山歴のある書き手を起用、編集者によると)その仕上がりは申し分のないものであったが、全体が登山家の視点で貫かれているため(略)人間臭いエピソードが全部落ちてしまったという。彼は(略)山の話としてではなく、人間の話としてまとめてみてはどうか、と勧めてくれたのである」
しかし、このことだけが動機とは思えない。
「この尖鋭的集団(小西が率いる山学同志会)は頑なに他との交流を拒み、日本山岳会に象徴される既成の権威に対して、エキセントリックといえるほど叛逆を試み続けた」「しかし私は、彼がわがものにした栄光にはさほど関心がない。ただただ叛逆の半生に心惹かれる」
一方、小西はこう言う。「僕の教育の仕方は、山の議論を一切させない。能書しか知らない耳年増になるだけですから」
本田は山にではなく、小西という人間に共鳴していたことが分かる。
小西は中学卒業と同時に就職する。銀座近くの印刷所である。昼には注文をとって弁当を買いに行く。真っ黒な作業着で銀座を歩く。最初のうちは恥ずかしかった。
小西が珍しく自伝的な部分を記した「凍てる岩肌に魅せられて」から―。「同窓会にある日顔を出してみた。卒業した麹町中学はいわばエリートコースであった。同級生の共通した話題は自慢話の一点に尽きていた。社会的に何も持たない私は軽蔑のまなざしで眺められる始末であった。しかし私は劣等感といった類のものはこれっぽっちも感じなかった」
小西がエベレスト第二次偵察隊への参加を承諾した時、慶応大出身で隊長の宮下秀樹は「どこのウマの骨だ」と言ったという。こうした権威に対する叛逆が小西の精神と肉体を鍛え、本田がそこに自分を投影したことは想像に難くない。
「栄光の叛逆者」のあとがきを本田はこう締めくくる。「小西氏の行動の軌跡は、私に生きることの意味を教え、勇気と励ましを与えてくれる。(略)私が登山家に期待するのは(略)俗界では見られない真に自由な人間の魂の輝きであり、非妥協的な自己主張なのである」
山の図書館~「氷壁」(井上靖著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「氷壁」(井上靖著) |
小料理屋ののれんをくぐる。「いらっしゃい。また山ですか」「奥穂へ登ったんだ」
こうして男と山と都会の関係が描かれる。
主人公の魚津とパートナーの小坂が凍てつく前穂東壁に挑むのは昭和30年の暮れから年明けにかけて、と設定されている。徳沢から奥又に向かい東壁をへて頂上に立つ。計画どおり元日午前8時きっかり壁の裾を登り始める。「ナイロンザイルは初めてなり」―。
「魚津はピッケルにしがみついていた。そして、小坂乙彦の体が彼の視野のどこにもないと気付いた時、魚津は初めて事件の本当の意味を知った」。ザイルはふっつりと切れたのである。
新潮文庫版「氷壁」 |
ナイロンザイルは当時、最新装備だった。従来のマニラ麻より強いと思われていた。魚津が切ったのではないか。小坂の自殺ではないか。小坂のザイルの結びが不十分で、不名誉を隠すため「切れた」といっているのではないか―。憶測が渦巻き、魚津は窮地に立つ。
ついには公開実験へと発展する。しかしザイルは切れなかった。20歳以上も年上の男性を夫とする美貌の女性、美那子は小坂との恋に悩む。小坂の妹かおるは魚津に恋をする。男女の関係が絡み合い、巧緻なプロットが組み上げられる。
厳冬の北アルプスの壁で起こった事件は、登場人物の心に「氷の壁」を作っていく。そう、タイトル「氷壁」は実は人々の心模様であることが分かってくる。
「(魚津は)問題の氷壁よりもっときびしい現実の上に立つぞと言った言葉を思い出した。確かにいま自分はあの白いごつごつした氷壁の一角に取りついている時と同じ気持ちだと思った」
遺体から収容されたザイルの切り口から、衝撃にもろい弱点が明るみに出る。しかしもう世間は関心を示さない。
かおるとの結婚を約束した魚津は滝谷を登り、徳沢でかおると再会する計画を立てる。約束を果たすため落石の中の登攀を強行、命を落とす。「静カナリ。限リナク静カナリ」と手記を残して。
昭和31年、朝日新聞に連載。この年、石原慎太郎の「太陽の季節」が芥川賞をとり、裕次郎が銀幕デビューした。日本隊のマナスル登頂もこの年だった。
山の図書館~松本清張「遭難」 [山の図書館・映画館]
山の図書館~松本清張「遭難」 |
東西冷戦を描いた「寒い国から帰ってきたスパイ」や「スマイリー」シリーズで知られる英国の作家ジョン・ル・カレは日常を描く名手だった。何気ない動作、せりふにこめられた布石が後段で極上のワインのごとく立ち上がる。たまらない魅力であった。
この感じ、日本で言えば誰だろう。その一人に松本清張を入れてもいいかもしれない。「張込み」や「点と線」で描かれる濃密な日常性と、立ちのぼるリアリティ。
その清張に唯一、山岳を舞台にしたミステリーがある。「遭難」である。
八月の鹿島槍で起きたある男性の死亡事故。新聞で報じられた後、同行の1人が山岳雑誌に手記を寄せる。山行にはもう1人、リーダー格の男性。いずれも同じ銀行の同じ支店に勤務する。
大町から冷池を経て鹿島槍。八峰キレットから五竜岳を経て遠見尾根を下る。「この予定は極めて普通のコースである」。山の情景と山行の模様が淡々と描かれる。
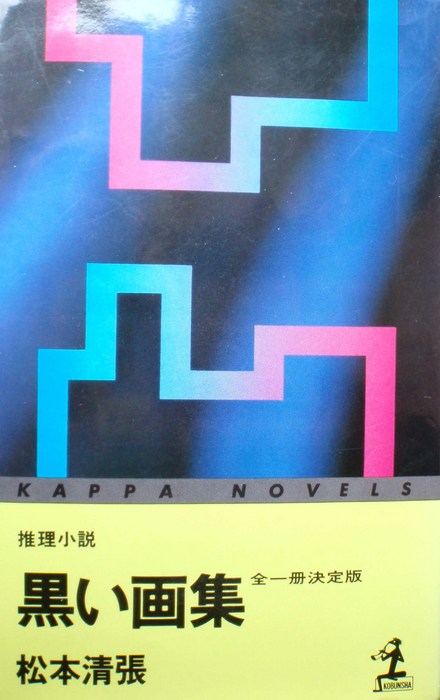 |
「遭難」が収められた「黒い画集」(光文社) |
「川の正面はV字型の山峡となり、その間に南槍と北槍の東尾根が高く出ていた」中を、たっぷりすぎるほどの休憩を取り、3人は登っていく。
翌朝、冷小屋を出たころから天候が悪化する。北槍を過ぎたあたりから風と霧が強くなる。尾根道の両方は急峻な渓谷。「引き返そう」。リーダーは決断し、ガスが濃くなっていく吊尾根を行く。
ところがここで尾根筋を見間違える。迷い込んだ先は黒部渓谷へと落ち込む稜線。夕刻、闇が迫る。2人を残し、リーダーは救援を求めて冷小屋へと向かう―。
遭難者の姉を名乗る女性から、リーダーだった男性へ電話がかかってくる。待ち合わせの場所には従兄と称する「おとなしそうな」男が同席している。男性と、冬の鹿島槍の慰霊登山の計画がまとまる。
男性は高校時代、山岳部にいたらしい。夜の新宿駅。手には手記が掲載された山岳雑誌が握られていた。あの山行のもようを事細かく頭に叩き込んでいたのである。そして手記に忠実に「慰霊登山」を実行する。2人の男の、絶壁の縁を歩くような心理戦。淡々とした前半部分に埋め込まれた布石が立ち上がってくる。
―あえて結末は書かないでおこう。今日あまたある山岳ミステリーの源流ともいうべき作品である。
1958年から60年まで週刊朝日に連載された「黒い画集」の中の一作。現在「松本清張映画化作品集」(双葉社)か新潮文庫「黒い画集」で読める。
山の図書館~「百名山の人 深田久弥伝」 [山の図書館・映画館]
「百名山の人 深田久弥伝」(田澤拓也著) |
「その大衆はやがて峠から嶺にかけての、あたたかい陽を受けたカヤトのあちこちに群がっていた。(中略)健康な青春謳歌の風景が展開されていた。もう私の頭から文学的・歴史的懐古など跡形もなく消えて、たださわやかな生命の息吹を感じるばかりであった」(「大菩薩岳」)
「日本百名山」に人間が登場する場面はあまりない。その数少ない一つ。一見明るく屈託ないが、実は視線はある高みにあり諦観にも似た影を感じさせる。なぜか。考えてみれば「山岳もの」を除いて、文学者深田久弥についてはほとんど何も知られていない。どんな作品を残しどんな道筋を歩いてきたのか。そんな疑問に答える1冊である。
東大から改造社に進んだ深田は昭和3年、懸賞創作の選考にかかわる。そこで入選を逃した一篇に心奪われる。「津軽林檎」と題した四百字詰め128枚。作者は北畠美代といった。病のため青森で幽閉状態にあった24歳の女性と文通を始める。4年後に「便り」を発表。叙情的な作品群の一つ「津軽の野づら」の原型になる。
| |
「百名山の人 深田久弥伝」(TBSブリタニカ刊) |
北畠と暮らし始めて、深田の作風は一変する。川端康成や堀辰雄、小林秀雄らの「文学」編集同人となり「津軽の野づら」は激賞される。
「けれども一般の読者や世間には、その奇妙な共同作業が知られるはずもない。(中略)深田と北畠の二人三脚はその後も続けられたのである」(「百名山の人」)
文芸評論家中村光夫の姉志げ子と約20年ぶりに再会したのは昭和16年。1カ月後、2人は雨飾山に向かう。翌年夏、長男誕生。背信が発覚し泥沼のさなか召集令状が舞い込む。復員した深田は志げ子と暮らし始める。
ヒラリーがエベレスト登頂を果たした昭和28年、「机上ヒマラヤ小話」を山岳雑誌に連載、単行本として刊行された。「日本百名山」は、その4年後に始まり昭和38年、50回で完結する。読売文学賞を受賞し選考委員の小林は「昔のことが思い出されなつかしい気持ちになりました」と、はがきを送る。
田澤によれば、深田久弥は高貴でも哲学の人でもなく不実と背信の人であった。しかし、そのことが「百名山」の価値を下げるわけではない。北畠の同郷人でもあった太宰治の言葉を借りれば「マイナスを集めてプラスにする」ことを引き受けた作品だったといえる。
山の図書館~ラインホルト・メスナー自伝 [山の図書館・映画館]
山の図書館~ラインホルト・メスナー自伝 |
8,000m峰全14座登頂、エベレスト無酸素単独登頂。いまさら説明するまでもない、傑出したキャリアを持つ登山家である。しかし、彼自身に対する評価はさまざまだ。毀誉褒貶といってもいい。その彼が人生を振り返った。
原題は「FREE SPIRIT A CLIMBER’S LIFE」。「自由なる精神」あるいは「自由を求めて」と訳せばいいだろうか。実は、この言葉の意味合いが著書の前半と後半で微妙に違ってくる。彼の精神の足取りがこめられているかのように。
イタリア・ドロミテの壁をくる日もくる日も登り続けた少年時代。「自由という地上の楽園にもっとも近いところにいるのが登山家」と語り、山頂に腰掛けて「無限の生命」と「一直線の未来への道」を感じる。そして、圧倒的なクライミングの記録が連なる。壁の小さな突起の一つ一つ、溝の具合、それらを微細に記憶し再現する。登山家としての才能とともに、その能力に舌を巻く。「(ぼくの講演を聞きにきた)彼らの見果てぬ夢を代わりに実現する役を引き受けたのである」という自負心がのぞく。
「ラインホルトメスナー自伝」(TBSブリタニカ刊) |
そのトーンが変化するのは、ナンガ・パルバットで同行した弟が遭難死してからだ。「冒険家とは職業でなく一つの生き方」と語り、哲学の影を帯び始める。エベレスト単独登頂の際の体験。標高7,800㍍でビバークしながら、脈絡なくある男を思い浮かべる。「(その男と)同様にぼくも頭がおかしいのだろうか」。そして山頂。「これ以上なにもできないことは分かっていた。できることは立ち上がってこの山を降りていくことだけだった」
40歳を過ぎた夏、チベットを徒歩で縦断する。「ヒマラヤより高い山に登ることは不可能だし単独行より少人数の遠征などありはしない」とするメスナーの一つの答えが語られる。野望もなく単に旅をする。(登山家としての)努力をやめたことでの平穏。自然回帰。南極に向かい、ひたすら歩き続ける。無窮のときの流れ。苦の絶滅=仏教の「滅諦」の教義への到達。
「超人」と呼ばれた男の栄光と苦しみがまぎれもなく、ある。
山の図書館~「凍」(沢木耕太郎著) [山の図書館・映画館]
山の図書館~「凍」(沢木耕太郎著) |
わずかに8,000㍍峰に届かず、エベレストのすぐ隣にあるがゆえに目立たない存在であるギャチュンカンはしかし、美しい北壁を持っている。標高差2,000㍍。その壁に魅せられた登山家夫婦の、死と向き合った苦闘の1週間を描いた一編。
著者は、ノンフィクションでもなくフィクションでもない手法でこの物語(あえて「物語」という)を仕上げる。例えば頂上を目前にしたシーン。
「しかし、山野井に降りるという選択肢はなかった。
山野井には登ったまま帰れなくなると知っていても登ってしまうだろう頂がある。
たとえばマカルーの西壁のような(中略)困難な壁を登った果ての頂上なら、その一歩が死につながるとわかっていても登ってしまうかもしれない。なぜならそれが山野井にとっての『絶対の頂』であるからだ。(中略)
ただ、頂を前にした自分には常に焦っているところがある、ということが山野井にはわかっていた。(中略)そこに確かな山があるとき、その山を登りたいという思いが自分を焦らせてしまうようなのだ」
憔悴、葛藤、苦悩、あらゆる内面の動きを、沢木は冷静な視線と引用文の少ない淡々とした文章で浮き上がらせる。登山とは肉体の動きであるとともに精神の営みであることを思い知らされる。 そして頂を極める。「早く頂上にたどり着きたい。しかし、この甘美な時間が味わえるのなら、まだたどり着かなくてもいい」という文章で始まる頂上直下の場面以降は、この上なく美しい。山野井は「高みから自分を見ている」という「神の目」を得て、文字通り「甘美」でさえある。
悪天候の中のクライムダウン。雪崩が襲う。標高7,500㍍、宙づりになったままのビバーク。死と直面しながらなお、断続的な雪崩をはるかに見て「崩れた雪が陽光にキラキラと美しく輝きながら氷河まで落ちていく」という感性。
山野井は現在、世界最強の登山家の1人に上げられる。それはなぜか、が肉体の強靭さだけではないところで語られる。山を知るとともに「読む」ことの楽しみを間違いなく味わえる作品である。
| |
沢木耕太郎著「凍」(新潮社) |
「凍」は2005年に新潮社から初版が出たが、その前年に山野井自身が著した「垂直の記憶 岩と雪の7章」(山と渓谷社刊)でもギャチュンカンの体験が語られている。読み比べても面白い。山野井を取り上げた著書としては「ソロ」(丸山直樹著、1998年山と渓谷社刊)がある。